 |
|||
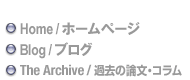
|
|
|
|||||||||||||
|
|
||
|
|
ハイテク日本危機の構図
1993年5月1日[中央公論]より 大幅な減収・減益。日本のエレクトロニクス企業の3月期決算に明るい材料はない。 企業各社の93年3月期決算見通しが発表され始めている。業界軒並みに減収・減益、日本を代表する大手エレクトロニクス企業もその例外ではなく、「半導体・コンピュータメーカーの先行きに明るさが見えない。大手5社(日立製作所、東芝、三菱電機、NEC、富士通)の93年3月期の経常利益は合計で前期比半減する見通し」(『日本経済新聞』3月2日朝刊)とある。もちろん、バブル経済崩壊後の93年3月期決算が決して明るいものにならないのは十分予測されたことである。ただ気になるのは、その原因を経済状況に求め、政策による解決に期待し、景気さえ回復すれば業績が上向きに転ずるはずだという楽観論が根強いことである。 しかし、半導体も含めたコンピュータ関連事業を大きな柱とするエレクトロニクス企業に関してはそのような楽観論はまったくあてはまらない。現在の不景気が仮に回復したとしても、企業業績の回復に直接つながることはあり得ない。それは、コンピュータ産業を中心とする関連業界において世界規模で起こっている激変が、日本企業に最も大きなダメージを与える形で影響するからである。さらにはっきりいえば、日本のコンピュータ・エレクトロニクス・ソフトウェア企業は、90年代半ばから後半にかけて深刻な経営危機に陥っていくに違いない。特にコンピュータ関連事業比率の高いエレクトロニクス企業ほど厳しい環境に直面しよう。そして小手先の解決策では効果がなく、21世紀に向けて日本企業がかつて経験したことのないような種類の挑戦に立ち向かう覚悟が必要である。このことが本稿の主題である。 つまり、ことコンピュータ関連産業においては、製造・生産技術や日本的管理方式や集団主義に代表される「モノ作りの強さ」を武器に、「製造業の復権」を期待することはできないのである。理由は大きく4つ挙げられる。この4つの理由については後で詳述するが、ここでまずポイントのみ簡単にまとめておきたい。 第1に、コンピュータ業界で大問題となっているダウンサイジング(コンピュータの小型化)現象、オープンシステム化の流れが日本市場においても不可避となったことである。コンピュータ産業が成立して以来業界を支配し続けてきた巨人IBM社が、91年度に赤字転落、92年度には単年度赤字49億ドル(約5800億円)に追い込まれたことは記憶に新しい。ダウンサイジング現象、オープンシステム化の流れがその原因を解説するためのキーワードである。簡単には、従来からのコンピュータ・ハードウェア事業、つまり「モノ作り」事業が利益の厚い儲かる事業ではなくなるという事実である。日本においてはまだこうした傾向が完全には表面化していないが、その影響が顕著に現われてくるのは、現在の不景気が回復して、企業が情報化投資を活発に再開し始める時と考えられる。 第2に、コンピュータ関連産業全体が、組織力を持った大規模な企業群によってではなく、小規模だが世界市場を視野に入れた個性的で活力ある新興ベンチャー企業群によって支配される世界に変貌を遂げつつあることである。その担い手のほぼすべてが米国ベンチャー企業であり、日本の大手企業には真似のできないようなダイナミックな戦略で、技術・顧客・業界構造の変化を推進させ、業界全体を牽引しているのである。日本にはベンチャー企業が育つ素地もなく、このことも大きな問題点として提起したい。 第3に、コンピュータ関連製品を構成する要素のうち最も付加価値の高い部分が、ごく少数の米国企業によって寡占されており、この構図が今世紀中は崩れそうもないということである。最も付加価値の高い部分というのは、「いかに作るべきかという実装・生産技術」ではなく「何を作るべきかのコンセプト」がポイントとなり、グローバル市場に通用するような製品・部品群のことである。たとえば、ハードウェアの心臓部に相当するマイクロプロセッサやソフトウェアの心臓部に相当するオペレーティング・システムが良い例だ。こうした「コンセプト指向グローバル製品」という領域に、日本企業はまったく参入できていないばかりか、その重要性を認識した上で経営努力を行なっている企業もほとんどないのが現実である。 第4に、技術・顧客・業界構造が激しく変化するコンピュータ関連業界においては、明確なビジョンを構築し、ビジョンをべースにトップダウンで企業を引っ張っていくリーダーシップが経営スキルとして不可欠だということである。日本企業にとって最も不得手な経営スキルといえよう。 これら4つの理由は相互に関連するものであるが、それぞれを詳述する前に、米国を震源として特にここ数年間で激しく変貌を遂げつつあるコンピュータ業界の全体像を概観してみることにしたい。
旧文化から新文化へ こうした絶え間ない業界構造変化の中でも最大の事件は、「コンピュータとは中央に存在して、皆で利用するものだ」という集中処理的な考え方(旧文化)から、「コンピュータとは1人1台所有して、必要なときだけ中央のコンピュータを利用すればよい。そのほうが価格も安いし性能も優れている」という分散処理的な考え方(新文化)に変化してきたということである。この変化は、70年代後半から80年代前半にかけてパソコンやワークステーションが登場した頃から徐々に芽生えてきたものだが、その機能・性能が著しく向上したことで、米国市場を震源に80年代後半に本格化し、今やグローバル市場に波及しつつある。現在コンピュータ業界で大問題になっているダウンサイジング(コンピュータの小型化)現象というのは、単にコンピュータの物理的小型化や価格低下のことだけを言うのではなく、この旧文化から新文化への移行のことを意味するのである。旧文化、新文化と表現したのは、技術、ビジネスの仕組み、主要な役割をはたす企業、どれをとってもまったく異なる世界であるからだ。旧文化的発想のままで新文化的事業を展開することは不可能だと言えるほど、両者の問には大きな溝があるのである。 旧文化的事業としては、その代表としてメインフレーム事業やIBM社を思い浮かべればよいが、特徴を一言で言えば、「コンピュータ・メーカーがユーザーに対して何から何までを提供する垂直統合型事業」である。ユーザー企業は自社の情報化投資の大半を、1つのコンピュータ・メーカー(たとえばIBMや富士通)に依存するという体質ができ上がった。つまり業界構造的に見れば、大手数社でコンピュータ関連業界が完全に支配されてきたのである。メーカーは、コンピュータの内部構造や基本ソフトウェアの詳細を外部に公開(オープン化)しないため、いったん導入したシステムをユーザーが利用し続ける限り、何もかもをそのメーカーに頼らざるを得なくなってしまう。こうして「メーカーがユーザーを抱え込む」ことで、利益の厚い儲かる事業を作り上げてきたのが、旧文化的事業である。冒頭で引用した記事中にある日本大手5社のコンピュータ関連事業の大半を支えるのは旧文化的事業と言えるし、不況感の強い日本のソフトウェア産業の大半も旧文化的事業なのである。
小規模でも個性的な企業が牽引する新文化 その結果として、IBM社などの超大手企業数社で業界全体が支配されるのではなく、業界そのものが断片化し、きわめて多数の個性的企業によって牽引されるようになった。これが新文化の最大の特徴である。多数の個性的企業からの個性的製品を結び付けて一体化させる「膠」のような役割を果すのが、「オープン標準」なのだと言ってもよいだろう。さらに、オープン標準自身がグローバル化するのにともない、特化したスキルを持ってグローバル市場をターゲットとする企業群が主役となる世界になってきたのである。 そしてもう一つ、新文化で忘れてはならない重要なポイントかある。このように業界が断片化してきたときに、付加価値も収益性も非常に高い事業と、付加価値も収益性も低い事業とに2極分化が起こってきたのである。そして、前者が米国企業に、後者が日本企業にという、日本企業にとっては好ましくない役割分担が進行中なのである。 たとえば、パソコンを構成する重要部品が、独立した業界として成立したことは最も顕著な例として挙げられる。つまり、ハードウエアの心臓部にあたるマイクロプロセッサや、ソフトウェアの心臓部にあたるオペレーティング・システムといった非常に付加価値の高い部品が、いわゆるパソコン・メーカーの手によって作られるものではなくなった。つまり、最終製品レベルではなく、高付加価値部品のレベルで「標準」としてグローバルに認知されてしまうと世界的な寡占状況が作られ、部品レベルでの超高収益事業が実現されるのである。 実例で言えば、NECのパソコンにも東芝のパソコンにも米コンパック社のパソコンにも、同じマイクロプロセッサ(米インテル社製)と同じオペレーティング・システム(米マイクロソフト社製)が搭載されている。「事実上の標準」をかち得た米インテル社、米マイクロソフト社は、純利益率で10数パーセントから20数パーセントという驚異的な収益性を示しているのである。知的所有権そのものを事業にしているとも言うべき新文化の特徴的事業なのである。 逆に、高付加価値部品レベルでの標準化が進むことで、コンピュータ・メーカーがいわゆる「モノ作り」で差別化することが難しくなり、最終製品段階での価格競争が激化し、従来型ハードウェア事業の収益構造が脅かされるようになってきた。確かに、日本企業は「モノ作り」については圧倒的強みを発揮するため、最終製品レベルでは競争力がある。しかし、高付加価値分を「標準」という名のもとで米国企業に取り上げられてしまった残りの「モノ作り」事業が、売上げが上がっても利益の薄い儲からない事業へと変化を遂げつつあるのである。
米国の旧文化企業は深刻な経営危機に
図1は、横軸に従業員数、縦軸に純利益率をとって、代表的米国企業の80年代後半から90年代前半までの業績推移を示したものであるが、旧文化の巨大企業がリストラ過程にある一方、新文化を体現する企業群のそれぞれが小規模ながらもいかに収益を上げているかがおわかりいただけると思う。さらに、図に載りきらないほど小さいが、意義のある収益性の高い事業を展開している個性的新文化企業が無数存在するのである。 ただ、新文化の個性的企業群も良いことばかりとはいえない。とにかく経営基盤が脆弱すぎるのである。「個性的」と言えば少しは聞こえがよいが、自社の強みを頼りに一発勝負を仕掛ける企業群だと評しても、あながち間違いとは言えないと思われる。たとえば、米国では新文化企業群の実態を「自然淘汰」(ナチュラル・セレクション)と称することがある。つまり一部の企業は大きな成功を収めるが、大半の企業が淘汰されてしまうほど競争が厳しく、成功確率が低いということなのである。「事実上の標準」をめぐる競争など、典型的なハイリスク・ハイリターンの世界である。最後に勝つのは1つの分野で1社かせいぜい2社で、その他大勢は敗退する世界である。IBM社をはじめとする旧文化大企業群は、こうした新文化企業群を横目で眺めながら、彼らの経営基盤のあまりの脆弱さゆえに、最後には自分たちが絶対に勝利を収めるに違いないと確信していたように思える。しかしこれも米国での3年前くらいまでの話で、現在は、どの企業がとは特定できないけれど、新文化企業群がコンピュータ関連業界を牽引していくのだという合意(コンセンサス)が、業界全体にでき上がっているように感じられる。このことが、日本企業や日本人にはきわめて理解しがたいポイントなのである。筆者は昨年1年間、勤務する経営コンサルティング会社のサンフランシスコ事務所に転籍して、シリコンバレーにある多くの新文化企業のコンサルティング・プロジェクトに参加する機会を得た。その経験の中で、痛切に感じたのがこの点だったのである。考えてみれば厄介な業界になったものである。 米国を震源として変貌を遂げつつあるコンピュータ業界の全体像を簡単にまとめれば、強固な経営基盤と組織力を持つ大企業が支配する旧文化的世界から、1社1社見れば心配になるほど脆弱な経営基盤しか持たないが、個性的で小規模な企業群の膨大なエネルギーによって牽引される新文化的世界へという大きな変化が、まさに進行中なのだということである。工業社会から知能社会への変遷を先取りしている業界と言うこともできるだろう。
旧文化的日本市場も景気回復後には変化が 第1の理由は、「旧文化から新文化への変遷」が日本市場においても不可避となったことである。景気が回復しユーザー企業が情報化投資を活発に再開した時に、投資は間違いなく新文化の分散システムヘとシフトするだろう。つまり、景気が回復した時点で、米国大手企業を襲った本質的構造変化の直撃を受ける可能性が高いということである。 1991年度のコンピュータ関連産業の売上げ高全体に対する新文化的事業の比率で言えば、米国市場がすでに60パーセントにまで達しているのに対して、日本市場ではまだ40パーセントにも満たない。日本におけるコンピュータの使い方は、米国ユーザーに比べて5年は遅れており、米国に比べればまだまだ旧文化の集中処理システムヘの依存度が高く、ちょうど米国の1987年頃の状況と非常に似ている。さてこの「旧文化から新文化への変遷」が大きく進むにはある種のきっかけが必要である。米国の場合、そのきっかけとなったのがブラック・マンデーであったと言われている。1987年に起きたブラック・マンデーの後遺症が癒えて、企業が活発な情報化投資を再開した時に「旧文化から新文化への変遷」が大きく進んだようである。経営環境が厳しくなり、しばらく情報化投資を控える間に、多くの米国企業が冷静に自社の情報化投資の方向を見定めた結果として起こった現象だった。今、不況下の日本企業でも同じことが進行中である。コンピュータの使い方における約5年の遅れと符合するように、ブラック・マンデーから約5年遅れで日本のバブル経済が崩壊したわけで、景気回復後には「旧文化から新文化への変遷」が日本でも確実に起こるに違いない。 では、「旧文化から新文化への変遷」が起こると具体的にどうなるのであろうか。旧文化の集中処理システムの売上げが伸びなくなることに加えて、コンピュータ・メーカーの収益性が著しく悪化するのである。コンピュータ・メーカーとは、コンピュータという最終製品を開発・生産・販売するメーカーという意味である。米国主要コンピュータ・メーカーのすべてが、5年前に比べて粗利率(グロス・マージン)が数バーセント低くても収益が出る体質の企業となることを目標にしている。粗利率は売上げ高に対するパーセンテージであるから、放置すれば同じ売上げを達成しても粗利率の低下する分だけ収益が圧迫される。このため、米国企業は人員削減や日本企業への製造・生産依託を含めた思い切った事業のリストラを実施することで、粗利率が低下しても収益が確保できるような企業体質への転換を企図しているのである。しかし日本企業の場合、米国企業のような思い切った人員削減を含むリストラは難しく、現在の事業規模を維持するために新しい収益源を求めて新文化に対応すべく努力していくに違いない。しかし実はそこにもう1つの大きな落とし穴が待っているのである(第2、第3の理由)。
大きいことが良いことではない これまでIBM社を含む巨大企業があれもこれもと多くの領域で競争してきたが、結局は特化した個性的企業に敗れてしまったのである。それは、大企業における組織のオーバーヘッドが大き過ぎることと、競合する小規模な企業に比べて意思決定プロセスに時間がかかりすぎるためである。また技術・顧客・業界構造が激しく変化するこの業界では、原則として将来は不確実である。不確実なことは承知で思い切った決断を迅速に下していくことが、小規模な企業群にしかできなかったのだとも言えよう。 日本のコンピュータ関連産業は、大手企業、それも総合エレクトロニクス・メーカーが中心的役割を果たしている。IBM社をはじめとする米国の大手コンピュータ企業に比べても特異なのは、コンピュータ関連事業に特化した企業すら皆無だという点である。重電、家電、通信、0A機器、電子部品といった事業も併せ持つ巨大組織によってコンピュータ関連事業が展開されていることが、別の意味で大きな問題なのである。量的な意味での組織の大きさに加えて、性質の違う複数の事業を有することによる組織の質的な複雑さが加わって、意思決定メカニズムが迅速に正しく働かなくなっている。その上、業界横並びであらゆる製品を作り、シェア争いを繰り広げ、成功を収めてきたという経験ゆえに、事業領域をしぼり込み特化して勝負するという決断は体質的になじまず、総花的に何でもやるという方向に向かいやすい。つまりこれまでどおりのやり方では、新文化的世界で日本企業が競争していくことは非常に難しいのである。 さらに、日本には米国のように活発なベンチャー企業がほぼ皆無であり、ベンチャー企業を育てる社会の仕組みも脆弱である。崩れかけているとはいえ終身雇用制も根強く人材の流動性も低い。日本から活発なベンチャー企業が生まれて新文化の担い手になるというのもすぐには考えにくいのである。しかも、仮に日本に優秀なベンチャー企業が多く存在したとしても、本当に付加価値の高い収益性の高い事業を目指すならば、グローバル市場をターゲットとしなければならず、そのためには、グローバル市場の約半分の市場規模を有する米国で成功することが不可欠なのである。
コンセプトなき日本企業の落とし穴
図2は、半導体を含めたコンピュータ関連業界をグローバルに見たときの概念モデルである。ある事業の特徴を考える上で、2つの切り口を導入している。横軸は「何を作るべきか」(コンセプト…概念)と「いかに作るべきか」(インプリメンテーション…実現、実装)のどちらがその事業にとって重要な要素なのかという視点を表わし、縦軸はその事業がどの程度グローバル性を持っているのかという視点を表わしている。図で示すように、このモデル上で、あらゆるコンピュータ関連事業を3つの事業タイプに分類できる。ローカル市場向げ事業、グローバル製造・生産事業、コンセプト指向グローバル事業の3つである。ローカル市場向け事業というのは、日本というローカル市場のみを対象とする事業のことである。グローバル製造・生産事業とは、半導体メモリ、液晶ディスプレイ、プリンタ、パソコン本体といった「いかに作るべきか」(インプリメンテーション)が鍵を握る製品をグローバルに供給していく事業のことである。コンセプト指向グローバル事業とは、マイクロプロセッサ、オペレーティング・システムをはじめとする基本ソフトウェア、汎用アプリケーション・ソフトウェアといった「何を作るべきか」(コンセプト)が鍵を握る製品・部品をグローバルに供給していく事業のことである。 結論から述べれば、日本企業が展開している事業のほぼすべてが最初の2つのどちらかで、高収益・高付加価値型のコンセプト指向グローバル事業にはまったく参加できていない。しかも新文化においては、日本企業が得意とする2つのタイプの事業環境が厳しくなり、コンセプト指向グローバル事業を空洞化させたまま高収益の事業を作り出すことは難しい。ここが新文化における日本企業の落とし穴なのである。旧文化においては、1つの事業や製品の中に、コンセプトの要素もインプリメンテーションの要素も1体になっていたため、その総体で競争すればよかった。つまり、コンセプト力の弱さを「モノ作り」の強さで補って余りある状況を作り上げ、競争に勝つことができた。しかし新文化では、前にも述べたようにコンセプト部分はコンセプト部分だけで知的所有権そのもののような事業として独立し、インプリメンテーション側に明るい未来が見えなくなってきているのだ。
厳しくなる目本企業のコンピュータ関連事業 後者の代表例として特に重要なのはパソコン事業である。日本のパソコン事業は新文化といえども、非常にローカル性の強い日本市場向け事業である。NECが50パーセント以上のシェアを持つのだが、その理由は「日本の特殊性」、つまり日本語処理能力が特殊なハードウェアによって実現され、しかもオープン化されていなかったからである。パソコン市場が立ち上がった頃の技術的にも未成熟だった段階においては、グローバル製品とは違う日本市場向けの特殊なパソコンが必要だったために、日本におけるパソコン事業はローカル性の強い事業として発展してきたのである。しかし、現在ではパソコンの基本性能が大幅にアップしたため、グローバル製品上でも十分日本語が扱えるようになり、そのための日本語オペレーティング・システム(DOS/V)が最近オープン化された。グローバル製品の場合、対象とする市場の大きさが日本市場に比べて圧倒的に大きく、規模の経済性が発揮され、低価格が実現される。最近、米コンパック社や米デル社製の日本語が扱えるパソコンが超低価格で販売され話題を呼んでいるのはこうした背景からで、明らかに「パソコン市場のグローバル化」現象が起きているのである。 では2つ目のグローバル製造・生産事業の現状はどうだろうか。作るべきものは決まっていて「いかに作るか」が勝負の世界であるから、日本企業の最も強い領域であり、貿易黒字の源泉でもある。アジア企業に対して今後とも十分な競争優位を持ち続けるであろう。コンピュータ業界におけるグローバルな意味での日本企業の役割として最大の期待がかかっている分野とも言える。ただここで間題なのは、日本企業間での過当競争体質である。確かに総体として、この事業が日本企業の独壇場であることは疑う余地がない。しかし個別にこうしたグローバル製品を見ていくと、A社にしかできないとかB社にしかできないといった製品・技術が非常に少なく、ある程度以上の企業ならば強い弱いはあっても誰にでもできる構造になっている。これまではこうした横並び型競争体質が技術革新を促進し、日本企業がグローバル市場を席捲する原動力ともなったのであるが、現在は日本企業間での過当競争が引き起こされ、売上げが上がっても利益が出にくい構造になりつつある。量産型で市場規模が大きく、売上げが期待できる分野では、同質の日本企業がひしめきあいながら競争しているからである。 また余談になるが、世の中の貿易統計は売上げをべースに計算されているため、収益性の低下という事情は統計数字に反映されることなく、売上げ高の上がるグローバル生産・製造事業を輸出の主体とする日本エレクトロニクス企業の貿易黒字は、なかなか減る方向にないのである。
超高収益の知的所有権型事業 これまでマイクロプロセッサやオペレーティング・システムの例を挙げてきたが、もう1つ、これからの巨大市場と見られるマルチメディア分野で見られる例を挙げてみたい。マルチメディア分野とは言うまでもなく新文化の世界である。今年2月のことであるが、ソニー、松下電器、AT&T、フイリップスを含む数社がマルチメディアで連合を組んだという記事が大きく新聞紙上を賑わした。しかし、この連合の中核には米ゼネラル・マジック社という頭脳集団企業が存在し、超高収益の知的所有権型の事業を企図していることを忘れてはならない。ゼネラル・マジック社とは、アップル社の天才ソフトウェア・エンジニアであったビル・アトキンソン氏が数年前に仲間と設立した新興ベンチャー企業である。この企業は、「マルチメディア情報を通信によってやりとりするための基本ソフトウェアの開発」にのみ特化専心している。そしてマルチメディア機器の開発・生産を行なう世界中の企業に対して、その成果物である基本ソフトウェア、つまり付加価値の最も高い部品をライセンス供与することを自社の事業だと規定している。つまり、この連合の真意は、数社の有力大手企業がゼネラル・マジック社の優れた基本ソフトウェアを、将来の自社ハードウェアに搭載することをほぼ決定したという意味である。パソコンの最も付加価値の高い部分が米インテル社と米マイクロソフト社に支配され、そこが収益性の源泉となってしまい、パソコン本体の事業が価格競争にさらされている現状をすでに指摘したが、同じ構図が将来のマルチメディア機器の分野で起こってくることは想像に難くないのである。 たとえばゼネラル・マジック社の基本ソフトウェアが搭載されたマルチメディア機器が市場に登場してくるのは90年代半ばから後半である。マルチメディア以外の分野でも、90年代半ばから後半に大市場になりそうなハードウェア機器の中核となる基本ソフトウェアや高付加価値半導体プロセッサについては、その標準化争いがもう繰り広げられている。残念ながら、その争いはほぼすべて米国企業間で行なわれており、日本企業は参加できていない。つまり今世紀中に大きな収益に結び付くような「コンセプト指向グローバル事業」には何の手も打っていないことになる。日本の大手企業は、この構図を21世紀まで続けて本当によいのか、真剣に考えるべき時に来ているのである。
ビジョンとリーダーシッブ コンピュータ関連業界で日本企業がこれから生き抜いていくためにどうしても必要なのは、米国のビジョナリーたちが考えるような深いレベルでのビジョンと、それに基づいてトップダウンに企業を引っ張るリーダーシップなのである。これまでの日本企業の経営リーダーシップの在り方を変えなければ、実現できないテーマだと言うこともできるだろう。
「挑戦する心」を またこれまで述べてきたように、コンピュータ関連産業は工業社会から知能社会へという「時代の歴史的変化の最先端」に位置しているとも言えるように思う。小手先の解決策ではなく、日本企業自らの根本的な変革が必要である。日本人中心主義、悪平等主義、横並び意識、個性・創造性の抑圧といった日本的経営の背景を見直し、新しい時代へ自ら変化していかなければならない。 実はつい先日渡米した際、昨年一緒に仕事をしていた同僚のアメリカ人やシリコンバレーの業界関係者たちに以上述べてきたような論旨を説明し、日本企業の将来について議論した。その議論でのわれわれの結論は次のようなものとなった。「確かに現状ではこれが正しい認識かもしれないが、21世紀までこの構図が続くかどうかはすべて今後にかかっている。日本企業がこうした現状を正しく認識すれば変化は可能であろう。これまで業界を牽引してきた米国企業のほぼすべてはゼロから出発した企業だし、これからもそうである。ゼロから出発する米国企業に比べて日本企業の強みは圧倒的だ。資金力、人材、技術力、どれをとっても一流である。すべては日本企業の今後の戦略次第。コンセプト部分が仮に日本人だけでできないとしても、世界中の優秀な人間と一緒になってやればいい。アメリカ人ばかりでなく、東欧の人でも旧ソ連の人でもアジアの人でもいいではないか。難しいことかもしれないが、とにかく挑戦(チャレンジ)するしか方法はない。世の中はもう変わってしまったのだから」。 しかし、日本社会や日本企業を熟知した日本の人たちとの議論の中からは、こうした結論はなかなか出てこない。戦略オプションをいろいろと議論していくと、「それは日本人にはできない」とか、「それは日本企業には無理だ」といった話がまず出てくる。本当にそうなのだろうか。われわれ日本人そして日本企業は、いつかどこかで「挑戦する心」を失ってしまったのではなかろうか。「挑戦する心」を失ってはこの世界では生きていけない。このことだけは肝に銘じておく必要があるのである。 ■
|
|
|
|
||
| ページ先頭へ | ||
| Home > The Archives > 中央公論 | ||
|
|
|
© 2002 Umeda Mochio. All rights reserved. |