 |
|||
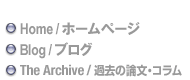
|
|
|
|||||||||||||
|
|
||
|
|
日本企業にシリコンバレーの活力を 1996年10月31日[日経ビジネス]より
1990年代後半に向かい、日本企業は「自社にとっての新しい未来をいかにして構築するか」という問題に直面している。既存事業だけに依存する体質では、これまでの資産を食い潰して生きていくといった縮小均衡未来しか描けないためである。そんな現状認識から、業績を回復し未来に目を向ける余裕が出てきた企業は、「新事業の創出」を最優先経営課題の1つに掲げて本格的に取り組み始めた。 数年前から騒がれ始めた「マルチメディア」という茫漠としたキーワードは、インターネットの全世界的普及という起爆剤により、ついにその正体を現しつつある。すべての人々、企業、行政機関などがネットワークによって接続されることで、我々の社会の仕組み、生活や仕事の仕方、メディアの姿などが大きく変貌すること、そしてこの変化に伴って生まれる新しい事業機会が膨大であること、しかし一方で衰退を余儀なくされる既存事業もたくさんありそうなことを、多くの人たちが認識し始めている。 この変化は、コンピューター産業やエレクトロニクス産業というコップの中の嵐ではない。通信、メディア、娯楽、教育、金融、小売といった多くのサービス産業をも巻き込んで新事業が模索される。新事業の大競争時代が始まったのである。 こんな大変化の震源に米国シリコンバレーがある。混沌としているが、次々に激しいスピードで、新しい技術や、新しい企業、新しいビジネスが生まれてくる。その秘密は何なのだろう。そんな視点から、シリコンバレーは日本で異常なほどの注目を集めることになった。 新聞社や雑誌社が支局を開き、新しい雑誌が発刊され、特集記事が増え、シリコンバレーの動向は逐一ウオッチされることになった。シリコンバレーに関する本は何冊も出版され、日本企業からの大量の出張者に加えて、財界などの視察ツアーも後を絶たない。表面的に調べられることは、もう全部調べ尽くしたという感すらある。 日本人がシリコンバレーを学びたいと思う動機は、閉塞感ただよう日本社会や日本企業にシリコンバレーのダイナミズムを何とか取り入れたいと思うからであろう。シリコンバレー的なやり方で、社会全体でいえば新産業を、企業の場合なら新事業を創出することで、明るい日本の未来を描きたいと思うからなのであろう。 シリコンバレー成長の原動力、ベンチャーキャピタルやベンチャービジネスの重要性を指摘する声も大きく、今や日本は「第3次ベンチャーブーム」だとまで言われている。高コストにも耐えうる付加価値の高い新産業・新事業を起業家精神の発揚によって作り出さなければならない。シリコンバレーへの注目は、先進国日本が今この課題に取り組まなければならないことを表している。 しかし、シリコンバレーを「頭で理解した」後に、本当に「身体が動く」のかどうか。勉強が終わって、それが行動に結びつくのかどうか。これからが、日本社会や日本企業にとっての本当の意味での挑戦だと言える。 日本の場合、元気のよい新しいベンチャー企業が次々に生まれ、そのことだけで経済が牽引されるという社会はすぐには考えにくい。優れた人材の宝庫とも言うべき既存企業が、自ら変革することによっても、新事業が創出されなければなるまい。 そんな流れの中で、真剣にこの分野での新事業を追求しはじめた日本企業の中に「新事業に対する経営の仕組みを根本的に変えることができなければ、成功はおぼつかない」と本気で考える経営者が増えてきている。言うまでもなく、日本企業的世界とシリコンバレー的世界とが、本質的に大きく異なっているためである。その違いを乗り越えて、日本企業にシリコンバレーのダイナミズムを作りこもうとする試みは、シリコンバレーを「頭で理解した」後に「身体が動く」ようにする「デジタル経営革命」と言い換えられるかもしれない。
シリコンバレーのメカニズム つまり、アイデアの多くが実際に市場で試されることで淘汰され、素晴らしい一握りの成功が生まれるという構造である。「新しい何かを創造する」という困難な営みのすべてが成功するわけがなく、成功物語ばかりに目が奪われがちなシリコンバレーには数多くの失敗の積み重ねがある。「確率の世界」とも言うべき環境が、うまく産業全体として回っている。そうした姿が、シリコンバレーのダイナミズムなのである。 こんな世界が成り立っている要因の1つに、「新しい何かを創造する」ことは偉いことなのだという価値観に基づいて、シリコンバレーすべてがデザインされていることが挙げられる。成功すれば大きく報われてよいのだ、という社会通念ができている。この価値観を誰もが信頼しているからこそ、アントレプレナーシップ(起業家精神)が生まれ、「新しい何か」が次々に作り出される。そうでないと、そもそも新しいアイデアが次々と大量に生み出されてくることがない。 しかし、それ以上に、数多くの失敗が不可避の「確率の世界」が、経済的にうまく回るメカニズムがあることのほうが重要である。その中核にNASDAQ(米国店頭市場)とベンチャーキャピタルという仕組みが存在する。ベンチャーキャピタルは別名リスクキャピタルとも言われる。「数多くの投資先が倒産・解散して投資が戻ってこなくても、一握りの投資先が成功すればその株式上場益によって損失をカバーできる」という前提に基づいて成立しているハイリスク・ハイリターン型金融機関である。この投資メカニズムが、「確率の世界」を経済的にうまく回している。
損失を出すたくさんの失敗を許容しつつ全体として収益を上げていく仕組み、つまり「確率の世界」を経済的にうまく回すメカニズムこそが肝腎なのである。 失敗確率が高いことは、数多くのトライアルがないと、1つも成功が生まれない危険があることを意味する。しかし、1つの企業の中で数多くのトライアルをすれば、より金がかかる。その多くが失敗すれば、せっかく一握りの新事業が成功しても、「焼け石に水」ということになってしまう。大丈夫なのだろうか。日本企業の悩みはそこからスタートする。シリコンバレーは株式上場益という「資産側での富の膨らみ」を原資としてたくさんの失敗を許容するモデルになっている。これに対して、通常の事業会社の場合、「事業が成功した際に生まれる事業利益」を原資にしたモデルで失敗を許容しようとするからである。 米国大手企業の新事業トライアルに対する最新経営は、「ベンチャーキャピタリスト対ベンチャービジネス」の関係を「経営トップ対新事業ユニット」に置き換えて、社内で数多くのトライアルが成立する仕組みを作るという考え方である。 経営トップがベンチャーキャピタリストの視点で新事業ユニットを見つけ、成功しそうなものを大きく伸ばす投資をしたり、成功しそうなもの同士を合体させて大きなシナジー(相乗効果)を生むよう仕向けたりする。その一方で、失敗しそうなものについては投資を冷徹にストップしてユニット解散・撤退の判断を迅速に下す。 ベンチャーキャピタリストにおける「株式上場による資産の膨らみ」を「事業が成功した際に生まれる事業利益」に置き換えて、経営トップがベンチャーキャピタル的新事業マネジメントを行う。「成功への重点投資による利益最大化と、失敗の早期発見・撤退判断による損失最小化」という組み合わせで、「確率の世界」を経済的にうまく回すメカニズムをつくろうとする経営手法である。 一方、日本企業の場合はどうか、従来、日本企業のキャッチアップ型新事業は、どこかに成功事例がある場合が多かったため、その成功事例を勉強し、新事業についての思考実験を繰り返し、事業化に着手するのが普通であった。こうした歴史的成功体験を持つ多くの日本企業の場合、せっかく筋のいい事業の種があっても、成功に対する強い確信が持て持てないと事業化トライアルすらしない、という現象が起きている。 この「成功に対する強い確信」というのが結構くせものだ。すべてが激しいスピードで変化し将来を予測することが難しいこの事業分野で、しかも創造的なことをしようとするならば、キャッチアップ型新事業と同等の「成功に対する強い確信」など、構造的に持ちにくくなっている。結局、日本企業の研究所ではたくさんの新技術や新製品の種が、事業部門の企画担当者の頭の中では、「やってみたいなぁ」と考えている事業の芽が、日の目を見ることなく時代の旬を過ぎていく。 ある日本企業の新製品プロトタイプを米国で事業化するフィージビリティー・スタディーの仕事をしたときのこと。わたしたちのコンサルティング・プロジェクトの過程で、新製品プロトタイプを見たあるシリコンバレーのベンチャーキャピタリストが、この製品の事業化に投資したいと言い出した。彼だけでなく米国市場関係者の反応は良く、私たちも自信を持って「成功可能性あり、ぜひ事業化を」と提言した。しかし、社内検討の末に下した日本企業の判断は事業化見送りであった。「成功に対する強い確信」が持てなかったというのがその理由であった。新製品に惚れたそのベンチャーキャピタリストは今でも残念がっている。 一歩進んで、成功の確信が昔ほどは持てなくても何か新事業を始めなければと考える企業でも、一度にたくさんの新事業を手掛けることにはまだ抵抗感が強い。とにかく一つ試してみて成功したらもっと大きく広げよう、という考え方が主流となっている。そのため、日本企業の場合ポツポツと新しい試みが見受けられるが、まだまだ全体的な大きなうねりにはなっていない。 数多くのトライアルが行われない最大の原因に、「失敗の早期発見・撤退判断」という経営機能が極めて弱いことが挙げられる。そしてこの弱みを根本的に解決しようと考えるのではなく、「いったん始めたらなかなかやめられない」ことを前提にして新事業経営を考えているケースが多い。つまり「いったん始めたらなかなかやめられない」から、「成功に対する強い確信」が持てる新事業だけに絞ってやりたい、と考えるのである。 この「いったん始めたらなかなかやめられない」という暗黙のルールは、減点主義と温情主義という不思議な組み合わせと「もったいない」という考え方によって生まれている。1つには、失敗・撤退イコール減点となってしまう世界で、撤退を短期で判断してしまうのは気の毒だから、しばらくの間チャンスを与えて、やりたいようにやらせてからでないとやめられないという論理。もう一つには、粘り強く続けてきたことの中にある素晴らしい何かを捨ててしまうのは「もったいない」という考え方が日本には根強いことである。 米国の著名な技術者から聞いた話だが、日本の研究所に呼ばれると「この技術にはもう何年もかけて、何億も投資している。この技術にこれからも投資しつづけることについてどう思いますか」という質問をよく受けるのだそうである。彼は決まってこう聞き返すのだそうだ。 「過去に投資したことをすべて忘れたと仮定して、その上で他の技術と比較して、それでもこの技術に今投資すべきだと思いますか」。研究所の人たちの答えはたいていノー。それでも日本企業はその技術に投資し続けるのが解せないと彼はつぶやいていた。 この「いったん始めたらなかなかやめられない」という暗黙のルールを引きずったままであれば、数多くのトライアルは絶対にできない。撤退ができず、失敗トライアルの多くが損失をたれ流し続けるようなマネジメント・スタイルでは、ごく一握りの成功によってその損失をカバーできるはずがないからである。 日本企業にシリコンバレーのダイナミズムをつくり込むためには、「成功への重点投資による利益最大化と、失敗の早期発見・撤退判断による損失最小化」という「確率の世界」のマネジメントの両輪をうまく回転させることで、数多くのトライアルが行われる創造型事業に適した環境を作ることが重要である。日本企業の場合、成功しそうなものにぐっと力を入れて伸ばすという経営機能は、得意とするところである。 「失敗の早期発見・撤退判断」という経営機能を強化し、「いったん始めたらなかなかやめられない」という「暗黙のルール」を意識的に破ればいい。そして事業トライアルの数が増えていく仕組みを作れば、創造型新事業がもっともっと生まれてくるに違いない。
バランスシート志向経営のダイナミズム 「しかし、こんなことではまだるっこしい。シリコンバレーが株式上場益という『資産側での富の膨らみ』を原資としてたくさんの失敗を許容するモデルになっているのならば、一企業内でも同じように考えたらよかろう。『事業が成功した際に生まれる事業利益』を原資にしようとするからシリコンバレーのスピードについていけないのだ」 こう考えているに違いないのが、積極的な投資・買収戦略で注目を集めるソフトバンクの孫正義氏であろう。 今シリコンバレーで、最も注目されている日本企業はソフトバンクである。ソフトバンクの孫氏は、米国で1000億円単位での巨額買収を続け、テレビ朝日株を取得し、デジタル衛星放送事業へ意欲を持ち、その一方で、約200億円程度を、ヤフー社を始めとする数多くのインターネット・スタートアップ企業に対して投資している。 事業会社というより投資会社ではないかという問いに、孫氏は「ある意味でその指摘は光栄である」(「日経ビジネス」96年8月26日号)と答えている。現象面をとらえると「孫氏はヘッジ・ファンドの帝王ジョージ・ソロス氏と同類であり、会社は希代のファンドマネージャーが率いる情報産業特化型国際投資信託、ソフトバンク・グローバル・ファンドである」「特異な財務構成は事業会社というより会社型投資信託に近い。創業以来の本業の出版や卸売り事業のキャッシュフローは資金集めの種銭で実態は金融業(投資業)である」(96年7月7日付日本経済新聞、末村編集委員)という指摘も極めて的を射ている。 ただ私はそれ以上に、孫氏の戦略には、本稿で述べてきた「シリコンバレーのダイナミズム」を一企業グループ内につくり込むための「壮大な実験」という側面を強く感じる。 孫氏は、自ら手がけた日本でのソフトバンク(ソフト流通・出版)事業と、買収によって得たコムデックスの展示会事業、ジフ・デイビスの出版事業、キングストンのメモリーボード事業を既存事業群と位置づけていると考えられる。そして、デジタル衛星放送とインターネット関連企業を、未来のための新事業ととらえているに違いない。 既存事業群と位置づけた買収先は、確実に今利益をあげている高収益企業を選んでいる。その一方で新事業と位置づける「まだ海のモノとも山のモノともわからない」インターネット・スタートアップへの200億円の投資は、ほぼベンチャーキャピタル同様の手法で、株式上場益という「資産側での富の膨らみ」を原資としてたくさんの失敗を許容するモデルを取っている。だからシリコンバレーと同様のモデルを一企業グループ内に作りこむことができている。 典型的事業会社がP/L(損益計算書)志向経営であるのに対して、ソフトバンクは既存事業に対しては大型買収、新事業に対してはベンチャーキャピタル型投資手法を用いるという思想で、B/S(バランスシート=貸借対照表)志向経営を貫いているわけである。 P/L志向経営に比べて、B/S志向経営は、賭け金の桁とその回収スピードが違うハイリスク・ハイリターン型だから、その戦略行動に危うさを指摘する主張があるのも当然である。
P/L、B/Sの絶妙な融合によるアドビ社のリスク低減戦略 ただ、典型的事業会社のP/L志向の新事業マネジメントに、ソフトバンク的B/S志向をうまく融合させることで、「シリコンバレーのダイナミズム」をつくり込もうとする試みは、ある程度の普遍性を持って議論できるのではないかと思う。 その観点から現段階で最も注目に値するのが、アドビ・システムズ社である。アドビ社も10年前はシリコンバレー・スタートアップであったが、いまや印刷・電子出版関連ソフトウエアのトップ企業、約700億円という売上高を誇る中堅企業に成長している。マイクロソフトにせよ、シリコングラフィックスにせよ、アドビにせよ、こうした急成長新興企業もまた、新しいスタートアップ企業から挑戦を受けている。 そのアドビ社が2年前に、4000万ドル(約37億円)の投資ファンドを作った。このファンドは、アドビ社の既存事業のために意義のあるスタートアップにしか投資しない。主目的を既存事業への戦略的貢献(P/L志向)としながら、副次的にファンド自身もきちんとROI(投資収益率)の形で純粋にリターン(B/S志向)を目指そうというものである。 これは、ベンチャーキャピタルの世界の用語では、ターゲット・ファンドといい、投資対象が狭く限定されているのでこれまではリスキーだと考えられていた。 ところが、アドビ社はこのファンドの投資先を自社の戦略展開に結びつけ、既存事業を大いに発展させるというP/Lベースの主目的を達成した。同時に21社の投資先のうち4社が株式公開を果たすという大成果をあげ、全米すべてのファンドの中でも第1位にランクされるという評価を得るほど、B/Sベースの副次的目的も達成したのである。 「P/L側ではなるべく絞りこんだ新事業展開を行い、そのために必要なたくさんのトライアルはB/S側をうまくレバレッジ(テコの原理の活用)する」という「P/LとB/Sの絶妙な融合」によって、「確率の世界」である創造型事業のリスクを低減するという経営手法は、間違いなく新しい息吹に違いない。 8月に発表された伊藤忠商事を含む10社が出資した総額1億ドル(約92億円)の「Java Fund」(ジャバ・ファンド)も全く思想で作られたターゲット・ファンドである。Javaは産業のマイクロソフト支配を打破する可能性を秘めている。サン・マイクロシステムズ、オラクル、IBM、ネットスケープといった反マイクロソフトの出資各社にとっては、切り札とも言うべき新技術である。そのJava言語を使ったインターネット・ソフトウエアを開発するスタートアップ企業のみを対象としたファンドを作ることで、Javaを早く世界標準にしようと考えているわけである。 Java周辺で数多くの事業トライアルが行われるようし、「確率の世界」の中から産業界に大きなインパクトを与えるような新アプリケーションや新技術を生み出そう。そのための素地を作るファンドなのである。
超経営イノベーション時代 私は、その5年間の成果として、社内での新事業開発、企業買収、ベンチャーキャピタル型投資の戦略的活用といった主題が浮かび上がってきたのではないかと考えている。そしてその主題をめぐって、超経営イノベーションとでも言うべき新しい経営手法が生まれつつあるのではないかと思う。 皮肉なことだが、その間、日本はバブル経済崩壊の後始末の中で、特にB/S側が裏目に出たときの怖さを身にしみて味わってしまった。その結果、米国で生まれた新しい経営手法を頭では理解しながらも、買収や投資といった「B/S側を積極的に活用する手法」には拒絶反応を持つ企業も多い。そのうえ、社内での新事業開発を考えた場合も、新しい人材の導入には消極的で、「現在いる社員の持つスキルの限界の中で」新事業を考えていくケースが多い。
日本企業がこうした現状を乗り越えて新しい未来を創るためには、多様な新しい経営手法の選択肢の中から、それぞれの企業がその経営観に基づいて、できることとできないことの仕分けをして、何がしかの勇気ある新しい経営手法を選び取っていくことが必要である。日本企業が本来持つ性格に、「シリコンバレーのダイナミズム」をどんな経営手法でどの程度加えていくのか、そのさじ加減が、日本企業それぞれの個性を創り出していくに違いない。
■ 掲載時のコメント:日本企業の生き残りのために、米国シリコンバレー企業の成功から学ぶ。そんな共通認識は生まれたが、具体的な企業改革には結びついていない。なぜか。シリコンバレーのダイナミズムを「身体」で覚えていないからだ。数多くの失敗に支えられた「確率の世界」では、とにかく試してみる。そして、事業利益だけではなく、株式上場などの資産のふくらみも活用すべきだ。
|
|
|
|
||
| ページ先頭へ | ||
| Home > The Archives > 日経ビジネス | ||
|
|
|
© 2002 Umeda Mochio. All rights reserved. |