 |
|||
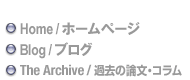
|
|
|
|||||||||||||
|
|
||
|
|
出口見えない消耗戦に突入した米国ハイテク産業 1998年3月2日[日経ビジネス]より
インターネット新時代の象徴的存在とも言うべき、シリコンバレーの急成長ベンチャー企業・ネットスケープが1997年度決算で赤字に転落、それも売上高5億3400万ドル(約670億円)に対して1億1500万ドル(約145億円)の純損失と赤字幅もかなり大きく、決算発表と同時に、人員削減を含めたリストラ案を発表した。94年4月に会社設立、その16カ月後には異例のスピード株式公開、その後96年初頭まで急騰した株価も今や「普通の会社」並みの水準で低迷し、「身売り話」までが報じられる昨今である。 大変なのはネットスケープばかりではない。94年から95年にかけて設立された膨大な数のベンチャー企業の大半が自然淘汰されたのは、「確率の世界」であるシリコンバレーの宿命だが、ヤフー、アマゾン・ドット・コムなど、勝ち残ってきた数少ない有望企業も、激化する競争環境の中、とても安閑としてはいられない。 また最近では、株価も高くキャッシュにも不自由しない現代ハイテク産業の覇者のマイクロソフト、インテル、シスコシステムズらが、有望ベンチャーを次から次へと買収し、「大手企業による技術独占の懸念」すらささやかれるようになっている。 シリコンバレーのベンチャー成長神話は、いったいどこに行ってしまったのだろう。彼らの信じた「インターネット新時代の到来」は、誇大妄想に過ぎなかったのだろうか。
最終的には1〜3社だけが生き残る 94年以来、この新しいビジネスチャンスをめぐって産業全体が試行錯誤を繰り返してきた。その結果はっきりしてきたのは、ほぼすべての新しい事業機会について、最終的には1分野に1社から2、3社だけが生き残る寡占型産業構造に向かうということだ。生き残るまでは大変だが、ある分野で生き残った暁には、競争者がそれまで作り上げてきた資産をも収奪し、市場支配力を持つことで高収益の強い事業を作り得る。加えて隣の分野に影響力を行使するパワーも持ち、M&A(企業の合併・買収)などの手法によって、その寡占事業の規模を大きくしていくこともできる。だから、そのいつか訪れる「素晴らしくおいしい」寡占を目指して、「体力勝負の果てしない消耗戦」が各分野で繰り広げられ始めたのである。
冒頭のネットスケープ苦境の原因は、ブラウザー分野での覇権を賭けてのマイクロソフトとの消耗戦にある。95年に80%の市場シェアを誇ったネットスケープに対して、マイクロソフトは「ブラウザー抱き合わせ」という独禁法違反で米司法省から提訴されるほどの激しさで挑戦。結局、両社とも「ブラウザーは無料」という最終兵器を出すことで、この「ブラウザー市場」そのものを焼き払ってしまったのだ。
「サーバーが厳しければ今度はサービスだ。ネットスケープほどのブランド力があ
現在の利益を犠牲にした長期戦 寡占の勝者になるまでの道のりが遠いのに、大企業とベンチャーの間で体力勝負の消耗戦が続けば、やがては体力のないベンチャー側の資金が続かなくなり、競争相手に買収されるか、築き上げてきた資産を売却しなければ、結局は立ち行かなくなる。 「会社丸ごとの身売り、または一部売却か」などという推測記事が書かれるのは、ネットスケープが直面するこんな現状を反映しているのである。 94年から95年にかけて、シリコンバレーでは、企業家精神あふれる人たちが「居ても立ってもいられない」といった気分で、インターネット・ゴールドラッシュに沸き、自宅のパソコンでホームページを立ち上げ、小さな会社を作って、インターネット上で新しいビジネスを始めようとした。ちょっと思い付いたビジネスのアイデアを、ホームページに表現して、世界中の人々が自宅のパソコンにアクセスしてくるのを待った。何万人、何十万人が、1人当たりほんの少しずつでもカネを払ってくれただけだって…。「とらぬ狸の皮算用」だが、皆がそんな夢を見た。しかし、そのほとんどの人たちに、夢の時は訪れなかった。 勝者と敗者を分けたのは、「徹底性」であった。「世界で一番になるまでやめないという強い意志」を持った人たちだけが、一般を広く対象とする大型サービス事業、限られた顧客層を狙ったニッチ型サービス事業の両方において、現段階まで勝ち残ってきている。 たとえば、「世界最大の書店」を標榜するアマゾン・ドット・コム。97年度の売上高は1億4780万ドル(約185億円)。すでに顧客数は100万人を超えた。2年半前にゼロからスタートしてこの数字は急成長に違いないが、97年度の赤字は2760万ドル(約35億円)と、まだ利益を出すには至っていない。彼らは、巨大な米国書籍販売市場約200億ドル(約2兆5000億円)の一角を占める寡占事業を作ることを夢見て、資金の続く限り走り続ける。 もう1つの例が、「オンライン証券取引」のE*Trade(イートレード)である。こちらも92年のサービス開始から約5年で、すでに顧客資産の預かり高は80億ドル(約1兆円)を超え、97年度の売上高は1億4270万ドル(約180億円)。純利益も1390万ドル(約17億円)と、利益を出しながらの急成長である。 この2社に代表される新分野とは、「既存産業の価値連鎖の全体を情報ネットワークシステムによって代替させてしまう事業」である。米国では「インダストリー・イン・ア・ボックス」という表現もあるが、そのユーザーとの接点の部分がインターネット上のウェブサイトという仕組みである。インターネット新時代のサービス事業の本流といっていい。
既存産業の代替を仕掛けるアマゾン・ドット・コム、E・Tradeのような会社は、1つの産業分野を選んで、「既存産業を代替する情報ネットワークシステム」に先行投資する。そして顧客を増やし、その分野での世界一を標榜し、寡占を目指していく。 中途半端な参入者は淘汰される先行投資は、ソフトウエア、コンテンツ、サービス、そしてコマース(商取引)の融合した情報システム、つまり知的構築物に対して行われる。だから寡占状況さえ生まれてくれば、限界製造コストはゼロとなり、「収穫逓増の経済」が働く世界になる。インターネットビジネスは、インフラ事業、サービス事業ともに、たとえば数百億円規模以上の大型事業機会については大企業による寡占、それ以下の「比較的市場規模の小さいニッチ型事業機会」については、そのニッチを「徹底的に極める」スペシャリストによる寡占という、どちらも寡占型産業構造に向かっていくと考えられる。ニッチの場合は、その世界を知り抜いて深く掘り下げていく者が勝者となり、「深さにおける徹底性」が競争優位の源泉となり、後発組の追撃は難しくなるだろう。いずれにせよ、中途半端な参入者はすべて淘汰されていくに違いないのである。 「寡占を目指しての体力勝負の消耗戦」が始まってしまったもう1つの理由は、大企業の経営観の変化にある。 IT(情報技術)産業における世代交代は苛酷である。第1世代の覇者IBMが91年に赤字に転落し、大リストラを敢行せざるを得なかったことは記憶に新しい。IBMをそこまで追い詰めた第2世代の旗手たちは、マイクロソフト、インテル、サン、コンパックといった設立10年から20年の新興ベンチャー企業群であった。 第1世代対第2世代の戦いは、ベンチャー側に軍配が上がり、敗者の失ったものは大きかった。90年代半ば、その第2世代新興ベンチャー企業群は、数千億円から2兆円という事業規模を誇る大企業になった。その時、インターネット新時代が到来、第2世代新興大企業群は、自分たちがIBMに仕掛けた挑戦と全く同じタイプの挑戦を、ネットスケープをはじめとする第3世代のベンチャー企業群から受けることとなったのだ。 マイクロソフト、インテル、サン、コンパックといった、今度は挑戦を受けて立つ立場になった大企業群は、世代交代の苛酷さを身にしみて知っている。ついこの間、自分たちが勝った競争と同じ競争の、ほうっておけば負ける側に身を置いているという認識があった。 だから「勝つために手段は選ばない」「やらなければ、やられるだけだ」「大企業がその強みを徹底的に突き詰めて、大企業にしかできないことをやってベンチャーとの競争に勝つのだ」、そんな強い意志を経営者が持った。ヒト、モノ、カネを持つ大企業が、徒手空拳のベンチャーに対して、時には「大人げない」ほどの競争を仕掛けてでも「勝ち」にいくべきなのだ、という経営観を持ったのである。その頂点にマイクロソフトのビル・ゲイツがいる。 その経営観を具現化した端的な例が、大企業自ら「ベンチャーそのものを次から次へと買収する」という「コロンブスの卵」のような経営戦略である。マイクロソフト、シスコ、インテルといった大企業が、「ベンチャーにできなくて、大企業にできることは何か」という問いに真正面から真剣に取り組む中で、最もシンプルで強引なやり方として、この経営手法を生み出した。目的は、新技術、新事業、人材の獲得である。 自社株を高く維持し、その自社株式とのスワップ(株式交換)によって、「才能ある若者たちが全力疾走した時間」を買ってしまうのである。 例えばネットワーク機器のある新分野で、戦略技術を持ったベンチャーをシスコが買収したとする。すると、「シスコと2社での寡占」を目指すスリーコムも、同様の技術を持った別のベンチャーを買収して、引き離されないようにする。しかし追随する3番手のベイ・ネットワークや、4番手以降の企業群には、もう買収に値するベンチャーは残っておらず、その新分野は諦めざるを得なくなってしまう。こんな競争が、至るところで起きているのである。 では今、米国のIT産業は何を夢見てこの消耗戦を戦っているのであろうか。何によって自らを奮い立たせながら、この苛酷な競争の日々を送っているのだろうか。 すべては、「パソコン産業勃興期の素晴らしい思い出」にその源がある。パソコン産業は、全く何もないところから、たったの20年たらずで何十兆円規模の巨大産業を生み出した。 この急成長の20年は、シリコンバレーのベンチャー・キャピタリストや起業家たちにとって「黄金の日々」であった。成功は、保有株式の信じられないほどの高騰という形で自分たちに戻ってきた。80年代前半、パソコン産業もこのへんがピークだろう、そんな産業観から、少し値上がりした保有株式を現金化してしまった人たちは、以来ずっと今日に至るまで心から後悔し続けている。この「パソコン産業勃興期の思い出」は、米国IT産業界の人々の胸に強烈な印象を残している。
インターネット信仰の行く先は 「3年で4倍の性能向上」という半導体における「ムーアの法則」(インテルの創業者、ゴードン・ムーアが唱えた法則)への信頼、それだけの技術革新を伴う供給があれば必ず需要が生み出されてきたという経験、そしてそのうえ、今度は通信のバンド(帯域)幅拡大が「新しいムーアの法則」として付け加わっていく。パソコン産業の時よりも、もっとすごいことがこれから起こるに違いないと信じているのである。 だから、業界全体の業績が一時的に悪化し、株価が低迷しても、「今は、消耗戦の真っ只中だから、そんなこともあるさ」くらいにしか考えない。 ビル・ゲイツをはじめとする「消耗戦を仕掛ける大企業側の経営者」たちも、ジョン・ドーアをはじめとする「ベンチャー企業に資金供給するベンチャー・キャピタリスト」たちも、パソコン産業に何が起こったかを身体が覚えているからその「極端なまでのサプライサイド経済観」は、容易なことでは揺るがないのである。 ただ、ここ数年で、シリコンバレーのベンチャー成長神話に変化の兆しが見えてきたことも事実である。 パソコン産業勃興当時には、シリコンバレーのベンチャーに立ちはだかるマイクロソフト、シスコのような強靭な新興大企業は存在しなかった。また、当時の産業全体のスピード感も今よりずいぶんゆっくりしていた。ネットスケープが誕生してまだ4年足らずだということを考えると、この間の動きは、まるでジェットコースターにでも乗っているかのようだ。 M&Aという経営手法が最近特に脚光を浴び始めた原因は、この現代のスピード感にある。これからも、「カネで時間を買う」経営手法・M&Aがフル活用された形で「寡占を目指す競争」が続いていくであろう。 そしてM&Aを実施しながら行き着く「寡占の勝者」のイメージは、プロ中のプロ経営者が率いる執行力に優れた組織で、困難なM&A後のマネジメントもきちんと執行できる大企業である。「Tシャツにジーンズで徹夜」といったシリコンバレー・ベンチャーがそのまま巨大化するベンチャー成長神話とはイメージがかなり違う。 では、シリコンバレーはどこに行くのだろう。その活力は失われてしまうのであろうか。 私は、「IT産業全体にとっての研究開発センター」という役割に、シリコンバレーは収斂しゅうれんしていくのではないかと思う。斬新な新技術、新製品、新サービスを生み出し、小さな事業ができあがったあたりで、どこかもっと経営力のある組織にその成果がなにがしかの形でバトンタッチされるというモデルが、今後はもっと一般化していくのではないかと思う。 パソコン産業は、「既存産業の横に」全く新しいカルチャーを持った独立した産業として根づくことになった。その過程でベンチャー成長神話が生まれた。しかしインターネット産業は、パソコン産業を含むありとあらゆる既存産業とのかかわりが深すぎて、「既存産業の横に独立して」ではなく、既存産業と融合する形で根づいていかざるを得ない。それもかなりのスピードでの融合が起こるから、ベンチャー自らが独力で成長することで、全く新しいカルチャーを持った産業を作る時間的余裕が生まれそうもないのである。 たとえばこれからのモデルとしては、ベンチャーが大企業に買収されるのもその1つだし、同種のベンチャー同士が合併した上で新しい経営陣を迎え入れて「次の段階」を目指していくという経路もあり得る。最初から大企業が支援するベンチャーも増えてくるだろう。 シリコンバレーをシリコンバレーたらしめているストックオプションなどのインセンティブ構造を壊してしまったら、「サプライサイド経済観」の拠り所となるイノベーションが起こらなくなってしまい、元も子もなくなってしまうのは、誰もが承知の上である。だから、シリコンバレーらしさを維持したまま、彼らが生み出す小さな成果を、経営執行力に優れた組織が大きく育てていくという産業の姿が、これから模索されていくのだと考えられる。
日本企業にもチャンスあり 新しい競争環境を理解してそれを執行に移し始めた「強い日本企業」と、従来のままのやり方で取り残されていく「弱い日本企業」。最近になって、日本のIT産業においてもこの二極分化の兆しが見えてきたのは、こんな背景からなのである。 また、サービス産業は顧客との関係が重要だから、元来ローカル性が高いビジネスである。特に日本の場合、「日本語を使う1億人以上の日本人」を対象とした、ローカルな大型サービス事業の可能性は極めて大きいといえる。インフラ事業の「事実上の標準」に比べて、海外の大型サービス事業がそのまま日本市場を侵食する姿は想像しにくい。その意味で、日本人を対象とした日本語によるインターネット・サービス事業は未開拓な巨大市場だ。 ただ、これまでのところ日本には、成功要因とも言うべき「徹底性」を追求している企業が少ない。その点で95年当時の米国市場の状況によく似ている。大型インターネット・サービス事業の構築には、ぴあのチケットぴあ、藤田田のマクドナルド・チェーン、セブン-イレブン・ジャパンのコンビニチェーンがスタートした時と同じような「スケールの大きな構想」が必要となってくるのだ。
いずれにせよ、知能工業社会における「21世紀の新しい産業の姿」をイメージしながらの苛烈な競争はまだ始まったばかりで、これからもしばらく続いていくに違いないのである。
■ 掲載時のコメント:米国のハイテク産業の間で体力勝負の消耗戦が始まった。インターネット事業がそうした消耗戦の舞台に。寡占の果実がとれるまで我慢する企業戦略が影響している。ベンチャー企業は先端産業全体の研究開発センターになる。日本企業は米国企業と協業すれば、まだ大きな事業機会がある。
|
|
|
|
||
| ページ先頭へ | ||
| Home > The Archives > 日経ビジネス | ||
|
|
|
© 2002 Umeda Mochio. All rights reserved. |