 |
|||
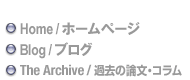
|
|
|
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
ウィンテルに崩壊の兆し パソコン産業、新時代に突入
1999年2月1日[日経PC21]より インテルがマイクロソフトを脅かす有力ベンチャーと組むなどパソコンの次をめぐって「ウィンテル」に異変が起きている。盤石とも思われたこの「基幹構造」が崩壊すれば、パソコン産業は全く新しい時代に突入することになる。 Duopoly(デュオポリー)。「2社による市場独占」がもともとの意味だが、コンピューター業界では、いつの日からか、インテルとマイクロソフトのことを表現する言葉になった。 Wintel(ウィンテル)。 辞書にも載っていないこの新しい造語が、ウィンドウズの「ウィン」とインテルの「テル」を意味することは、もう誰もが知っている。 パソコン産業が本格的にスタートしたのは、IBM-PCが発売された1981年からだが、言うまでもなく、その中核部品であるマイクロプロセッサーとOSを担当したのがこのインテル、マイクロソフトの二社である。以来17年間、「ウィンテルによるデュオポリー」は、パソコン産業における最もおいしいところをしゃぶり尽くしてきた。パソコン産業の酸いも甘いも知り尽くし、卓越したリーダーシップを発揮する経営者のもと、手を携えて乗り切れる危機ならば必ず行動を共にしてきたインテルとマイクロソフト。 この2社の関係に大異変が起きている。「パソコンの次」(After the PC)をめぐって、インテルがマイクロソフトから少し距離を置き、独自の道を歩み始めたのだ。 論より証拠。インテルの戦略転換という視点からパソコン産業のここ数カ月の動きを見てみよう。 (1) Linuxを中心とする「オープンソース」的世界の勃興がマイクロソフトにとって最大の脅威であることは、既に本誌11月号(98年9月末発売)の本欄で詳述した。その号が発売された直後の9月29日、インテルは、Linuxの販売・技術サポートを手がけるベンチャー企業、レッドハット・ソフトウェア社に資本参加した。この出資においてインテルが行動を共にしたのは、マイクロソフトではなくその宿敵ネットスケープであった。 (2)11月16日、インテルは、「BeOS」というマルチメディアOSを開発したベンチャー企業ビー社(Be Inc.)に資本参加したことを発表。BeOSは、その技術的秀逸さゆえ、シリコンバレーではかなり昔から注目を集めていた。しかし如何せん、OS分野での新規参入はリスキーすぎ、技術がいくら優れていてもマイクロソフトの牙城を崩すのは難しいとの評価が大方の見方であった。 インテルは、1990年代初頭に「アーキテクチャ・ラボ」という組織を作り、年間平均にして1億ドル以上の資金を投じ続けてきた。この組織は、インテル・チップの周辺で事業展開をはかる企業群の視点から、パソコンのアーキテクチャーが進化・成長を続けていく上での障害を取り除いていこうというミッションを持つ。新市場を創造するアプリケーションや周辺機器などを手がける企業群と一緒になって、どんな技術的課題が解決されれば、パソコンの周辺に新市場が次々と創造され得るのかを研究してきた。 そしてその過程で、インテルはかなり多くのベンチャー企業に資本参加してきたが、OS分野で、あからさまにマイクロソフトを脅かす有力ベンチャーに出資することはなかった。 いわばこれまでの出資が「ウィンテルによるデュオポリー」を維持発展させるための投資だったのに対して、レッドハット社とビー社への出資は、「ウィンテルによるデュオポリー」が崩れた時の保険としての投資なのである。 (3) 10月中旬、テレビ局のインタビューに答えて、IBMのガースナー会長は、「PCの時代は終わった」と発言。パソコン以外の情報端末の重要性が高まるパーベイシブ(広範な)・コンピューティングが、これからの成長分野となるという見方を示した。 パーベイシブ・コンピューティングの構成要素は、インターネット携帯端末、電話の延長線上のスマート・フォン、テレビを高機能化させるセットトップ・ボックス、ネットワークに対応した自動車などなど。これまでもずっと注目されてはきたが市場が立ち上がっていない諸製品である。しかし、こうした非PC端末のすべてがネットにつながれる時代が到来すれば全く新しい価値が生まれ、これからは本格的に市場が立ち上がってくるという読みだ。 マイクロソフトはウィンドウズCEを中核とした戦略でこの分野に攻勢をかけているが、そのパートナーとなるチップメーカーはインテルだけとは限らない。非PC分野CPUで市場シェアの高いミップスや日立、インテルと競合するアドバンスド・マイクロ・デバイス(AMD)社など、マイクロソフトは有力チップメーカーのほぼすべてと提携関係にある。 (4) 下表は、九八年八月の米国パソコン小売り市場・売り上げベスト七である。まず驚くのがインテルのシェア低下の激しさである。この売れ筋七機種のうち、インテル・チップは、第二位の「コンパックPresario 5030」(ペンティアムII 300MHz)と第四位の「コンパック Presario 5020」(セレロン 300MHz)の二機種だけ。AMD社のK6シリーズが第一位「ヒューレットパッカードPavillion 6330」を含めて三機種、ナショナル・セミコンダクター社のサイリックス・チップが一機種、モトローラ社のパワーPCが「アップル iMac」一機種となっている。
98年8月の米国パソコン小売市場・売上ベスト7
(5) 表で気がつくもう一つの大きな異変は、パソコンの売れ筋価格帯の下落である。アップルコンピュータ起死回生のヒット商品「iMac」の1299ドルがこの中で最も高く、4機種が1000ドルを切っている。加えて、10月以来、大手メーカーによる低価格パソコンの発表が相次いでいる。コンパック、IBMの家庭用デスクトップマシンの最低価格機種は、それぞれ699ドル、599ドルと驚異的な安さである。 パソコンという商品は、「売れ筋商品の価格帯はあまり下がらず、同じ価格帯の製品の性能が飛躍的に向上する」という性格をずっと持ち続けてきた製品である。それは、「三種の神器」(ワープロ、表計算、データベース)に加え、DTP(デスクトップ・パブリッシング)ソフト、ゲームソフト、各種業務用ソフトなど、「買った時点では使わなくても、将来使うかもしれないアプリケーションソフトが豊富に揃う可能性」を、顧客がパソコンに求めていたからであった。買ってから半年後に出るソフトが動かないのは困るから、ある程度上位の機種を買っておいた方が安全だと、顧客は考え続けていたのである。 しかし98年のパソコン売れ筋価格帯の下落は、このセオリーが通用しない世界に入ったことを意味している。 ポイントは、「パソコン上のアプリケーションソフトの可能性」よりも「インターネット上でのコンテンツやサービスの可能性」の方が大切になったことだ。パソコンにとってのキラー・アプリケーション(つまり何の為にパソコンを買うかの動機)が、「三種の神器」をはじめとする「パソコン上のアプリケーションソフト」ではなく、ヤフーやアマゾン・ドットコムのような「インターネット上でのコンテンツやサービス」だと考える顧客が激増したのである。 「インターネット上のコンテンツやサービス」を求めてパソコンを買うのならば、パソコン本体の構成は必要最小限のものでいい。本体の性能ばかり高くしても、インターネットへのアクセス速度が追いつかなければ何の意味もないからだ。 パソコン産業も、ついにインターネット時代到来による変化の大波を受けはじめたのである。 インテルとマイクロソフトの微妙な新しい関係は、10月19日に始まったマイクロソフト独禁法違反裁判にも大きな影を落としている。そもそも司法省が97年10月、マイクロソフトに対して訴訟に踏み切った時点では、「マイクロソフトがOS(ウィンドウズ)の独占状況を武器に、パソコンメーカーに対して、無料ブラウザーの『抱き合わせ』を行なったことの違法性」が問題とされた。 しかしインターネット産業のスピードは極端に速い。97年10月の提訴からほんの数カ月後、マイクロソフトの攻撃ターゲットとなったネットスケープは赤字転落、戦略を大きく転換してポータル(本誌98年8月号参照)事業を中心とした成長戦略を描くこととなった。その一環でブラウザーの完全無料化に加え、ソースコードまで公開する(本誌11月号参照)という大胆な施策を打ち出した。そして11月24日、ついにアメリカ・オンライン(AOL)によるネットスケープ買収という衝撃的なニュースが世界を駆け回った。 簡単にいえば、97年10月時点での争点は、問題自体がもうほとんど消滅してしまったのである。もちろん違法性はあったかもしれないのだが、昔にさかのぼって競争状態を元に戻すことは不可能になってしまったのだ。 そんな背景から司法省は、「ブラウザー抱き合わせ」という個別問題で裁判をやってもあまり意味がないので、マイクロソフトのこれまでのビジネス慣行のほぼすべてに対して独禁法違反を適用する方針をとっている。司法省側の証人には、ネットスケープのみならず、アップル、サン・マイクロシステムズ、アメリカ・オンラインといったIT関連の主要企業がずらりと並んだ。そんな中に、「ウィンテルによるデュオポリー」の盟友インテルの名もあった。 10月19日から始まった裁判の第一週のハイライトがネットスケープ社CEOのジム・バークスデール氏の証言、第二週のハイライトはアップルのテヴァニアン副社長の証言、第3週には「知らない」「覚えていない」を連発するビル・ゲイツのビデオ証言が一部公開された。各社の証言では、次から次へとマイクロソフトの独占パワー行使の実態が明らかにされている。 そして第四週に入った11月9日、いよいよインテルのマクギーディ副社長が証言台に立ち、マイクロソフトと真っ向から対決する立場での証言を行なった。 司法省が証明したかったのは、「95年時点でインテルはインターネット関連ソフト(音声・ビデオ関連技術)の開発プロジェクトを進めていた。このインテルのプロジェクトに対して、マイクロソフトが、『我々がPC関連ソフトのすべてをコントロールするのだから、インテルはソフトから手を引け。手を引かないのならば、インテルの新製品開発に協力しないぞ』という圧力をかけた」という点であった。 そもそもこの裁判でマイクロソフトが問われているのは、「OS独占という強大なパワーを不当に行使して、産業における健全な競争を阻害したかどうか」である。 しかし難しいのは、マイクロソフトには、「独占にあぐらをかき、競争を妨げ、自分だけはのんびりと楽をして、高価格を維持し、顧客の犠牲の上で収益を上げる」という過去の独占企業のイメージが微塵もない点だ。 マイクロソフトが「競争を妨げている」ことは事実だとしても、「独占にあぐらをかき、自分だけはのんびりと楽をして、高価格を維持」しているわけではない。莫大な研究開発投資を行ないつつ、産業界の誰よりも「競争的」だし、ブラウザー無料化などは高価格維持の正反対であるからだ。 そして最も大きな争点で、しかも意見が分かれているポイントは、マイクロソフトが「顧客の犠牲の上で収益を上げている」と考えるべきか否かである。 この観点でインテル証言には重みがあるのだ。なぜなら、ネットスケープという先行者を追い上げるべく後発者としてのマイクロソフトが猛追した場合は、競争が著しく促進された挙げ句に製品が無料化されてしまったのだから、「顧客の犠牲はない」という論理が成立する。しかし先行者であるマイクロソフトが後発者インテルの参入に不当な圧力をかけたとなれば、「本来存在すべきであった競争」が妨げられ、「顧客に潜在的被害を及ぼした」という論理が成立するからだ。 まだまだ裁判は始まったばかりである。これからも見どころはたっぷりある。日本での報道量はさほど多くないが、米国報道機関のインターネット報道は実に充実している。興味ある読者は、インターネットでのマイクロソフト独禁法関連サイトを是非のぞいていただきたい。 いずれにせよ、「ウィンテルによるデュオポリー」こそが、パソコン産業の産業構造のエッセンスである。ここが崩れれば、どんなことだって起こり得る。 このデュオポリーに亀裂が生じはじめたのが1998年だったとすれば、1999年はパソコン産業が全く新しい時代に突入していく元年だと言えるのである。 ■
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ページ先頭へ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Home > The Archives > 日経PC21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
© 2002 Umeda Mochio. All rights reserved. |