 |
|||
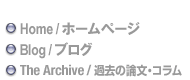
|
|
|
|||||||||||||
|
|
||
|
|
「ニュー・ニュー・シング」の魅力とシリコンバレーの本質
2001年1月29日[BizTech eBiziness]より
本欄「「ニュー・ニュー・シング」を読もう」でマイケル・ルイス著「ニュー・ニュー・シング」についてご紹介してから約1カ月が過ぎた。 前回の寄稿では、読者の皆さんにあまり先入観を持ってもらいたくなかったので書かなかったのだが、私が「ニュー・ニュー・シング」を推薦したのは、著者ルイスが「シリコンバレーの中核に渾然一体として存在しているとんでもなさと尽きぬ魅力を、ジム・クラークという人物を通して描ききることに成功している」と感じたからだった。 ただ、その話をする前に、この1カ月を振りかえってみれば、私の友人や本欄担当の山岸君から感想文をもらったり、eコマースに関するメーリングリスト上で議論されている内容を読んだりして、大変面白かった。 サンプル数はそう多くなかったが、この本についての感想が、真っ二つに分かれていたからだ。山岸君を含む二十代の人たちからの評判はあまりよくなく、私と同世代または少し上のシリコンバレー通の人たちからは、逆に圧倒的な支持を得た。 山岸君の分析によれば、彼自身を含む不満派のポイントは、 (1) 多くの日本人にとってはジム・クラークもハイペリオン(ジム・クラークのヨット)も特別ではない。特にIE登場以降にインターネットを使い始めた多くの若い世代にとっては、ネットスケープやジム・クラークについて強い思い入れがない。 (2) だからなぜこの本がジム・クラークとハイペリオンに執拗にフォーカスするのかがわからない。 (3) むしろ、ネットスケープとインターネットエクスプローラーとの競争やマイクロソフトの独禁法違反訴訟、ヘルシオンなどインターネット史上の大事件の数々についての描写が中途半端で概要がつかめないので、結局この本は何が言いたかったんだという不満を抱かせる結果となっている。 の3点だという。 それに加えて、自分の20代の頃を思い出して考えてみるに、 (4) 若いときの読書というのは、今、自分にとって具体的に必要な何か(情報や刺激やエネルギー)を得たいという欲求に導かれている場合が多いから、シリコンバレーとは何かを文明論的な視点からも考え抜き、文学作品としても成立させようと意図する著者、マイケル・ルイスの「余裕や遊びの部分」にあまり共感できなかった。 のではないかと思う。そしてその「余裕と遊びの部分」というのは、ルイスがシリコンバレー初体験で驚嘆したり抱腹絶倒したりしたことのエッセンスがまとめられているところなので、これは、シリコンバレー通の人たちからの強い支持とも裏腹になるのだが、
(5) シリコンバレーと一度でも真剣に付き合おうとした人でないとなかなか実感できない「シリコンバレーの本質的なとんでもなさ」がたくさん書かれていて、その部分が面白くて面白くてたまらないという性格を持っているので、いくらネットの世界に興味があっても、身体でシリコンバレーを体験したことのない若い人にとって、その部分が全くぴんと来なかった。 ところでこのジム・クラークが作る世界初のコンピュータ制御のヨット、ハイペリオン。ルイスは、このハイペリオンという「とんでもない存在」に出会って本書を書く決心がようやくついたに違いなく、当然のことながら、このヨットは本書で実に重要な役割を果たしている。 シリコンバレーの「とんでもなさ」を描こうとすると、たいていの場合は失敗に終わってしまう。それは、「とんでもなさ」を安易に描くと、「とんでもなさ」と一体になっている「凄さ」とそれゆえの「尽きぬ魅力」を描くことができなくなってしまうからである。逆にシリコンバレーの魅力をただ礼賛すると、現実に起きている「とんでもないことの数々」を無視するか、奇麗事として描かざるを得なくなり、奥行きを失った作品になってしまう。 ルイスは、そのことについて悩んで悩み抜いたに違いなく、何百人もの起業家にインタビューした末に、「でも、1冊の本を支えられるようなキャラクターには出会えなかった」(訳者あとがき)という。そしてルイスはジム・クラークと出会うわけだが、そのときクラークは「世界一高いマストを持つヨット、ハイペリオン号を動かすためのコンピュータ・コードを、配下の若きプログラマーたちと書いているところ」(同)で、ルイスはなぜか「不快感を覚え」(同)、「でも、それは興味深い不快感でした。砂粒がこびりついた牡蠣のような。付き合っていくうちに全世界がその砂粒にこめられていることが明らかになりました」(同)と述懐する。 ルイスの不快感の源泉は、クラークが持つ「抜群の才能と、自らの才能への自信(過信)」「自分のことしか考えない身勝手」「技術に対する異常なまでの偏愛」「普通の生活では消費しきれず暴発しそうになる過剰なエネルギー」「凡庸な人間に対する強い軽侮の情」「体制に対する畏怖の気持ちの欠如」「社会全体への関心の欠如」といったことの融合だと想像できるが、クラークの持つこの特質のすべてが、シリコンバレーを象徴するものでもあり、なおかつシリコンバレーの魅力の源泉にもなっていることに、ルイスはいつしか気づくことになる。 ルイスは、1年間の長きにわたって「クラークの人生に相乗りして過ごし」(同)、深い取材を行ない、本書「ニュー・ニュー・シング」で、ジム・クラークとハイペリオンを描いた。その結果、シリコンバレーの中核に渾然一体として存在している「とんでもなさ」と「尽きぬ魅力」を同時に描ききるのに成功したのである。
シリコンバレーを動かす中核の本当に凄い連中は、実はいろいろなことについてあまり何も考えておらず、本書が描くクラークのように、ただ無邪気に遊んでいるだけなのである。 そしてさらに、その中核と周縁の間に存在する「才能という名の残酷な溝」(スケールの大きな天才とその一歩手前の間の大きな違い)を描くことにも、本書は大きな成功を果たしていると言えるだろう。 ぜひ皆さん、「ニュー・ニュー・シング」を読んでみてください。 ■
|
|
|
|
||
| ページ先頭へ | ||
| Home > The Archives > BizTech eBiziness | ||
|
|
|
© 2002 Umeda Mochio. All rights reserved. |