 |
|||
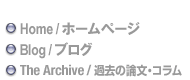
|
|
|
|||||||||||||
|
|
||
|
|
コンピュータ日本まだ起死回生の秘策はある
1993年12月1日[中央公論]より IBM社の凋落に象徴されるコンピュータ産業の激変のなかで、同様に苦境に喘ぐ日本の各メーカー。だか、忘れてならないのは、コンピュータ産業が間違いなく成長産業だという事実だ。「後ろ向き」の不況対策だけではない再生のシナリオがあるはずだ。 「景気さえ回復すれば」という声も近頃はあまり聞かれなくなった。内需不振に加えての急激な円高で、不況が長期化しているからである。経費・設備投資・研究開発費の削減では追いつかず、雇用調整も本格化の兆しを見せている。新聞紙上で、「希望退職」「人員削滅」「採用抑制」といった見出しを見ない日のほうが少ない。中でも、日本の経済成長の原動力であった自動車産業、エレクトロニクス産業までが雇用調整を検討せざるを得なくなってきた。日本が強いと信じていたこうした産業の国際競争力に陰りが見えてきたことは、出口のない不況感の一因ともなっている。日本のコンピュータ産業を取り巻く環境の厳しさもその例外ではない。輸出比率が低いため円高の影響は他産業に比べて小さいが、それ以上に米国を震源とした産業構造変化の大きな影響を受けている。IBM社の凋落に代表される産業構造変化が、コンピュータ産業では進行中なのである。 しかし、忘れてならないのはコンピュータ産業が間違いなく成長産業であるという事実である。この産業にはまだまだやるべきごとがたくさんあり、発展の余地も大いにある。ただ、これまで正しいと信じていた枠組みが崩壊し、過去の成功体験が無用の長物となる世界に突入しようとしているだけなのである。つまりコンピュータ関連企業にとって、立ち行かなくなった事業を「再建」することは急務だか、同時に市場創造型の成長戦略をも描かなければならない。成熟産業においては、その不況対策が「後ろ向き」の施策に偏りがちで、産業全体が萎縮方向に進みやすい。しかしコンピュータ関連企業は、単に萎縮するだけでなく、産業構造変化の影響を克服することで新しい産業を興すのだというくらいの気概を持つべきである。 本稿ではこうした視点から、本誌5月号に発表した「ハイテク日本危機の構図」でまとめた日本企業の本質的課題を克服するための戦略・構想を詳述していきたい。
コンピュータ産業の構造変化 IBM社といえば、コンピュータ産業が成立して以来、牽引車として業界を支配し続けてきた超大企業である。そのIBM社がこれだけのリストラクチャリング努力を余儀なくされ、それでもなお、現在コンピュータ業界で起こっている大激変には対応しきれてはいない。ダウンサイジング、オープンシステム化といったキーワードに象徴される、コンピュータ産業の歴史始まって以来の大事件が起こっているからである。「コンピュータとは中央に存在して、皆で利用するものだ」という集中処理的な考え方(旧文化)から、「コンピュータとは1人1台所有するものであり、必要なときだけ中央のコンピュータを利用すればよい」という分散処理的な考え方(新文化)へと変化していることが表面的な原因である。しかし加えて、この産業が工業社会から知能社会へという「時代の歴史的変化の最先端」に位置しており、「工業社会での覇者」が知能社会でも生き抜いていくための自己変革を行なっている過程だとも考えられる。 この変化の影響は日本企業にとっても多大である。放置すれば、IBM社と同様、日本のコンピュータ関連企業もまもなく深刻な経営危機に陥っていくに違いない。日本の半導体・コンピュータ・メーカー大手5社というのは、日立製作所、東芝、三菱電機、NEC、富士通のことだが、この5社の93年3月期決算の経常利益は、合計で前期比半減以下となった。好調な重電部門を持たない、いわばコンピュータ関連事業比率の高いNECと冨士通の業績の落ち込みはとくに著しかった。そして依然として業績回復の兆しは見えず、「富士通の93年9月期の中間期の連結最終損益は500億円前後の赤字になる見通し」(『日本経済新聞』8月17目朝刊)に代表されるように、先行きは決して明るくない。 そもそも日本のコンピュータ産業は「IBM社に対抗して国産コンピュータ・メーカーを育成し、日本市場だけはIBM社の支配から守りたい」という認識を立脚点としていた。40年にわたる日米コンピュータ戦争は、IBM社対日本の大手メーカーという構図で繰り広げられてきた。結果的に世界中で日本だけが、IBM社に国内市場を独占されずにすんだことはよく知られている。しかし、多大な成果をあげ成長を遂げた日本メーカーにとって不幸だったのは、対IBMという旧文化的枠組みの中での競争に明け暮れている間に、新文化的世界が米国を震源として勃輿し、世界を席捲してしまったことである。競争の前提が崩れてしまったのである。新文化的世界を作り上げる立役者となったアップル社、サン・マイクロシステムズ社、マイクロソフト社といった米国企業が創業されたのが70年代後半から80年代前半、現在の繁栄の基盤が作られたのが80年代前半であった。このもっとも大切な時期に、当時の日本メーカーは対IBMという戦いに全精力を注ぎ込まざるを得なかった、ここに悲劇の源泉があったという見方もできる。
「ハイテク日本の衰退」を避けるために
図1は、前稿でも用いたが、日本メーカーのコンピュータ関連事業を議論する上で有効なモデルである。このモデルを使って日本メーカーを取り巻く現状を簡単にまとめておこう。横軸は「何を作るべきか」(コンセプト…概念)と「いかに作るべきか」(インプリメンテーション…実現、実装)のどちらがその事業にとって重要な要素なのかという視点を表わし、縦軸はその事業がどの程度グローバル性を持っているのかという視点を表わしている。このモデル上では、あらゆるコンピュータ関連事業を、日本というローカル市場のみを対象とする日本市場向け事業、半導体メモリ、液晶ディスプレイ、プリンタ、パソコン本体といった「いかに作るべきか」が鍵を握るハードウェア製品をグローバルに供給していくグローバル製造・生産事業、マイクロプロセッサ、オペレーティング・システム、汎用アプリケーション・ソフトウェアといった「何を作るべきか」が鍵を握る製品・部品をグローバルに供給していくコンセプト指向グローバル事業の3つに分類できる。 日本メーカーの得意とするコンピュータ関連事業は、日本市場向け事業、グローバル製造・生産事業のいずれかしかなく、高付加価値のコンセプト指向グローバル事業はほぼすべて米国企業に握られており、この構図が今世紀中は崩れそうもない。加えて、得意としてきた日本市場向け事業、グローバル製造・生産事業の事業環境も、ユーザーの変化や円高や日本メーカー間の過当競争体質などの構造的要因ゆえに、今後はますます厳しくなっていくことが予想される。これが日本メーカーにとっての厳しい現実なのである。 こうした環境下においての日本メーカーの戦略・構想は、短期的視点と中長期的視点とに分けて議論しなければならない。短期的な課題は、これまで得意としてきた日本市場向け事業と、グローバル製造・生産事業をいかにしてリストラクチャリングしていくかである。そして中長期的な課題は、いかにしてコンセプト指向グローバル事業に足掛かりをつかんでいくかである。それぞれ一つずつ詳述していきたい。
ユーザーが大きく変わろうとしている 米国では80年代後半から、日本でも最近になってこのシフトが顕著なものとなってきているが、ユーザー側で起こっているこの現象は、まさに「旧文化から新文化への変遷」そのものであり、それにともなうメーカーの盛衰と表裏一体をなすものなのである。IBM社、富士通、日立製作所といったメインフレーマーの売り込み先は、ユーザー企業の情報システム部門であった。メーカーの社員がユーザー企業の情報システム部門に常駐する例も多く見られるほど、ユーザーに密着した形で、コンピュータを供給するだけでなくアプリケーション・ソフトウェアの開発も請け負い、付随するサービスも提供し続けてきた。一方、エンド・ユーザー部門では、自社のメインフレームの機種にはお構いなしに、自分たちの問題解決に役立つパソコンやワークステーションを導入するのである。中央集権から分権への変化がユーザー側に起こっているとも言える。ユーザーが大きく変わろうとしているのである。そしてユーザー企業にとってのこれからの最大の関心事は、企業内のあらゆるコンピュータ資源を統合して全社的な情報インフラを構築することにある。しかしその実現は難しく、そのための道筋を明確に描き切れているユーザーはほとんどいないのが現状である。 ソフトウェア・サービスで収益を上げる仕組みを こうしたユーザー企業の実状に合わせて、日本メーカーにも戦略転換が必要である。自社製品だけをユーザーに売り付けようとせず、ユーザーの求める他社製品も含めて統合情報システムを構築する方向に戦略転換しなければならない。これが日本市場向け事業を再生させるポイントである。事実、多くのメーカーがその方向を標膀してはいる。しかし、このことは日本メーカーの取ってきた戦略を根底から揺さぶる問題を引き起こすのである。 メインフレームやオフコンといった旧文化のコンピュータ・システムの内部構造や基本ソフトウェアの詳細は、原則として外部に公開(オープン化)されていないため、他社のパソコンやワークステーションとの接続が難しい。情報公開をしないことでユーザーを囲い込み高収益をめざす体質が、依然色濃く残っているのである。ユーザー企業では、エンド・ユーザー部門が積極的に導入してきたパソコンやワークステーションと、情報システム部門が管理するメインフレームとが統合できないという悩みを抱えている。こうした状況をメーカー自ら打破していかなければならないのである。 旧文化体質においては結果として、ソフトウェアの1円入札事件が好例だが、ソフトウエアやサービスをほぼ無償で提供しても十分に見合うほどハードウェア価格が高く設定できていた。またシステムがいったん導入されれば将来にわたっても同じユーザーに対して、自社製の高価なコンピュータを提供し続けることができた。ハードウェアもソフトウェアも、システム総体として一括で管理され「システム全体として売り上げが上がれば長期的に見て必ず利益が上がる」構造が作り上げられてきたのである。 しかし、価格競争が激しく粗利率も低いパソコンやワークステーションの比率が高いシステムが主流となり、他社製品も必要に応じて調達しなければならないとなると、こうした考え方では通用しない。つまり、システム総体をユーザーに提供する際に、その都度、ソフトウェア・サービスの採算をハードウェアとは切り離してきっちりと管理していかなければ「売り上げが上がっても利益が上がらない」構造に陥ってしまうのである。 一方、ユーザー・サイドにも、ソフトウェア・サービスに対して対価を支払うという習慣が、日本では根づいていない。メーカー側も「ソフトウェアやサービスは無償に近い形で何とかします」ということで高価なハードウェアを長いこと売り続けてきたため、ハードウェアが安くなって儲からなくなったからといって、「その分をソフトウェア・サービス代で」というのではユーザー側も納得しないのである。ソフトウエア・サービスの価値は、突き詰めれば人材の価値である。ハードウエアとは分離した形でソフトウエア・サービスに正当な対価をユーザーから支払ってもらうためには、優れた人材を集め、その価値を高める仕組みを作り、「ソフトウェア・サービスの価値」という面でのブランド・イメージを確立し、その価値を「安売り」しないと決めることが肝要である。こうした方向へといかに自らの事業を変身させていくかが鍵なのである。 このことを実現していく上で最大の障害として立ちはだかってくるのが、工業社会における成長路線を支えてきた年功序列・終身雇用を柱とする日本メーカーの雇用慣行である。システム設計、ソフトウェア開発といった領域における個人の能力格差はきわめて大きい。知能社会における特徴とも言える。社歴や労働時間の長さによって給与格差が決まってくる現制度では、優秀な人材が生きない。外部の優秀な人材を中途採用して活用していく仕組みは皆無に近い。年俸制の導入が進んできたといっても、「人が人を評価する」という経験が組織全体に根づいていないため、実際には大して機能しない。日本メーカーは、こうした諸問題を時間をかけてでも克服していくことが必要なのである。 コンピュータ事業の本格的グローバル展開を 日本メーカーにとって短期的にもうひとつ重要なのが、グローバル製造・生産事業をいかにしてリストラクチャリングしていくかである。そのためのポイントは2つある。第1に、パソコン及びワークステーション事業に対して、多くの日本メーカーが非常に中途半端な形で取り組んでいるが、グローバル化に本気で取り組むか、開発・生産から撤退するかの二者択一の決断をすることである。第2に、これから勃輿する新しいハードウエア事業に対しては、市場か立ち上がってから参入してシェア争いをするというこれまでの考え方から脱却し、市場を創造する段階から積極的に関与していくことである。それも市場はまず米国で創造されることが大半であるから、米国での市場創造活動に真剣に参加していくことである。 まずパソコン、ワークステーション事業のグローバル展開の問題から考えていきたい。これまで述べてきたように、日本のコンピュータ産業は「IBM社に対抗して国産コンピュータ・メーカーを育成し、日本市場だけは米国勢の支配から守りたい」という認識を立脚点としてきたため、日本メーカーには開発・生産したコンピュータを世界に向けて販売していくという意識が希薄だったのである。また、メインフレームを中心とする事業の形態は、ユーザー企業と密着して大規模プロジェクトを遂行するという性質のものであり、グローバル展開がしにくかったことも事実である。しかし、新文化のパソコン、ワークステーション事業は事情が違う。たしかに、付加価値の大部分をマイクロプロセッサやオペレーティング・システムといった知的所有権型事業に持っていかれて収益性は以前より低くなった。しかし依然として成長性の高い事業であり、やり方次第で成功が見込める分野である。日本メーカーの活躍の場はまだまだあると考えられる。グローバル市場で高いシェアを持つことができれば、知的所有権型事業をめざす米国ベンチャー企業に対してもバーゲニング・パワーが生じてくる。コンピュータがコモディティ化した今こそが、日本メーカーにとっての新しいチャンスだととらえることもできよう。グローバルにみたパソコン、ワークステーション市場において、日本メーカーの存在感が薄いことのほうが不思議なくらいなのである。 日本メーカーがこれまでグローバル化にまったく取り組んでこなかったとは言わないまでも、その趣旨は日本メーカーが開発したコンピュータを自信を持って世界に展開しようというものではなかったと思う。一部の例外はあるが、日本メーカーのパソコン、ワークステーション事業は日本市場向けに行なわれてきたと言っても過言ではない。同じエレクトロニクス機器といっても、ビデオ等のオーディオ・ビジュアル機器、コピーやFAXのようなオフィス機器とは状況がまったく異なっているのである。 グローバル展開を指向しなければならないもう一つの理由は、日本市場のみを対象としたパソコン事業やワークステーション事業がこれからは成立しなくなるという環境変化である。米国を中心とするグローバル市場をターゲットとして本気で闘っていく意志がない限り、成功の見通しが立たないことを認識しなければならない。技術的に作れるからといって日本市場のみを対象に事業化しても、「売り上げが上がっても利益が上がらない」構造に陥ってしまう。グローバル市場を対象として生産された製品に対して、規模の経済性という観点から競争力を持ち得ないためである。グローバル展開を本気で行なっていくための第1歩は、設計・開発機能と販売マーケティング機能を米国に持ち、日本にいる技術陣がそれを後方から支援する体制を作り、生産は世界中でもっともコスト競争力のある所で行ない、米国市場で成功することである。そのために何より重要なのは、意思決定機能を米国に移すことである。日本市場については、米国市場で成功した製品を日本に持ち込むという構図の中で考えるべきである。グローバル展開への強い意志と体力がないメーカーは、日本市場のみを対象とした中途半端なパソコン事業、ワークステーション事業から撤退すべきである。競争力のあるパソコンやワークステーションを他社から調達し、ソフトウエア・サービスでユーザー企業を満足させる方向に付加価値を求めなければなるまい。 市場創造に積極的に関与すること ハードウェアのグローバル製造・生産事業のリストラクチャリングに関わるもう1つのポイントをまとめたい。冒頭で述べたように、コンピュータ関連産業は言うまでもなく成長産業である。まだまだ未知の分野も多く、新しい事業機会がこれからも次々に生まれてくるに違いない。ソフトウェア分野に隈らず、ハードウェア分野にも大いに期待できる。ここで日本メーカーが真剣に考えなければならないのは、これから立ち上がる新分野のハードウエア製品群については、市場が立ち上がってから参入してシェア争いをするという考え方から脱却して、市場を創造する段階から積極的に関与していくように方針変更すべきである。それも市場はまず米国で創造されることが大半であるから、米国での市場創造活動に真剣に参加していくことである。市場創造は1社ではできないため、米国企業との戦略提携がきわめて重要になる。当面は米国企業が市場創造の主役であることは否めないが、日本メーカーが得意とする技術力を戦略提携を通して、市場の創造にどう結びつけていくかが鍵である。市場創造には関与せず市場が立ち上がったのを見計らってから参入するのでは、創業者利得が得られず、「売り上げが上がっても利益が上がらなく」なる。
図2は、われわれがコンサルティング・ブロジュクトを進める時に活用する「コンピュータ関連製品のライフサイクル・モデル」である。ライフサイクルの第1段階は「実験段階」である。技術の可能性が検討される段階である。研究所で研究が行なわれている従来製品は、おおむねこの「実験段階」にあると言ってよいだろう。自動翻訳電話などが好例である。第2段階は「特定領域での商品化段階」である。コストはともかく技術的に実現できることが確認されれば、「費用はある程度かかっても欲しい」という市場をターゲットに商品化される。音声認識システムなどはまだまだ広くは利用されないか、軍用機の操縦などの特定用途向けに実用化されている。第3段階は「市場離陸段階」である。コストが下がり、より広い応用分野が特定きれれば、大きな市場として立ち上がる。そして第4段階が「コモディティ化段階」である。どんな製品を作ればよいかは誰にとっても明らかになる。市場規模もある程度以上大きくなっているので、日本メーカーをはじめ多くの企業が参入してくる。継続的な改良・改善、コストダウンの競争となる。 さて、このラィフサィクル・モデルにおいて、第1段階から第3段階までが「市場創造のゲーム」、第4段階が「市場シェア獲得のゲーム」と分けて考えることができる。米国ではよく「市場調査レポートかすでに市販されるようになった市場に参入しても、もう儲からない」という言葉が使われる。市場調査レポートが市販されるのは、一般に「市場離陸段階」の少し前くらいである。その時点ではすでに、市場が立ち上かった時の勝者の構図がほぼ固まっているという意味である。つまり、ライフサイクル・モデルにおける第1段階、遅くとも第2段階から参入して「市場創造のゲーム」から関与していかなければ、採算の合う事業を構築することはできないのである。「市場創造のゲーム」が繰り広げられている間に、核となる技術を取りまくさまざまな「事実上の標準」が決まってくるからである。そのプロセスに身を置きながら、戦略部品の提供やグローバル製造・生産技術といった市場創造に必要な要素を主体的に提供していくことが重要なのである。 レーザープリンタ市場において、日本メーカーの中でキヤノンだけが依然として大きな市場シェアを確保しているのは、DTP(デスクトップ・パブリッシング−机上印刷市場)を「創造するプロセス」に米国で深く関与したからである。市場創造の段階では、当面の市場規模はきわめて小さく将来の市場規模も不確定要素が大きすぎて予測不能である。これまでの日本メーカーは多くの場合、売り上げ高至上主義が根強かったため市場規模が小さい段階では参入しなかった。つまり米国で市場を創造していく段階からは積極的に取り組んではこなかった。これからはその姿勢を変えていかなければならないのである。 米国でインサイダーとして生きていく決意 これまで述べてきた2つのポイントは、グローバル製造・生産事業のリストラクチャリングを考えていく上で重要な考え方だが、そこに共通するキーワードは、米国市場に対するより真剣な取り組みである。米国でインサイダーになって活躍していくことである。生産拠点を移管するとか販売拠点を持つという程度のことではなく、設計開発も含めて事業部をまるごと米国に移管するくらいの覚悟が必要である。日本人だけでやっていくのではなく、アメリカ人や世界中から米国に集まってきている優秀な人材とも一緒になって生き抜いていく方向を、真剣に模索していくべきだと思う。容易なことではないが、実現に向けて努力すべき課題である。 日本メーカーの現在のグローバル・スキルは、生産拠点の経営と販売拠点の経営までにとどまっている。研究開発、新技術をべースとした新製品企画、顧客や競合企業との共同開発、市場創造をめざしたマーケティング活動、標準化への取り組みといった、日本人以外のレベルの高い人材と一体になって努力していく能力を必要とする活動は、事実上行なわれていない。行なわれていても成功している例はきわめて少ない。また意思決定プロセスが、多くの関連部署の合意や企業全体の雰囲気がべースとなって決断が行なわれる。新しいイノベーティブなアイデアが、即断即決で実行に移されることはほとんどない。たとえば、米国駐在の日本人企画スタッフや日本メーカーの米国法人に勤めるアメリカ人のチームからせっかく新しいアイデアか生まれても、事情をよくわかっていない日本側の関連部門がいろいろと口を出す。あちこちで摩擦を起こしかねないような決断は先送りされ、「前例にないから」とか「他社がやっていないから」という理由で何も始まらない場合が多い。また決断までの時間がかかりすぎ、市場環境の激変に合わせてダイナミックな決断を迫られる状況には対応できないことになる。 しかし、こうしたグローバル・スキルと意思決定プロセスの問題は、変革不可能な根本的問題ではない。突き詰めていけば、企業家精神が発揮できない体質に陥っている日本メーカーの仕組みや、できることなら過去の成功体験のままにやっていきたいという日本人の心の在り方に問題があると思う。しかしこうしたことは、組織全体に活力を与え得る創造的ビジョンと、それに基づくトップの強いリーダーシップによって解決可能な問題なのである。 中長期的にはコンセプト創造型事業を そして日本メーカーにとっての中長期的な課題は、コンセプト創造プロセスに深く関与していき知的所有権型の事業を持つことである。新しいコンセプトを創造し、世界に向けて発信していくことである。成功すれば「売り上げに対する貢献は大したことはなくても利益に対する貢献はめざましい」事業になる。ただ、今世紀中に大市場になりそうなハードウェア機器の中核となるコンセプト指向グローバル製品については、残念ながらもう日本メー力ーが参加する余地はない。しかし21世紀まで現在の構図を引きずらないためにも、日本の大手メーカーのうち数社には、いまからでも真剣な取り組みをしてほしいと思う。 ますますの円高も手伝って、先進国である日本のメーカーが、現在以上に創造的付加価値を高めていかなければならないことは明らかである。ただ一方で、これまでだって製造・生産現場を中心にして日本人の創造性は大いに発揮されてきたという議論があり、どんなに苦しくても日本メーカーは将来の糧となる研究開発費の削減はあまり行なわない方針を崩していないのだから、いずれは何とかなるという議論もある。問題の本質は、日本メーカーの研究開発がどうしてもインプリメンテーションを追求する傾向が強く、コンセプト思考の創造性を発揮する枠組みができていないことである。 インプリメンテーション指向とは、課題がかなり明確になったところからスタートする研究開発である。努カ賞の世界であり、組織的に着実にまじめに努力することで日本メーカーは大きな成果を生み出してきた。一方、コンセプト構築とは、じつに荘洋としたところから考え始める作業である。成功の保証はなくリスクの大きい研究開発である。たとえばアップル社が市場に投入した携帯用情報機器「ニュートン」のコンセプト構築は、「人間がいかに情報を使って仕事をするのかを完全に認識しよう」というところからスタートし、数年の歳月を費やした上で製品化されたのだそうである。努力よりもセンス、組織的管理よりも個人の才能に依存する研究開発だと言うこともできる。コンセンサス・ベースでやるものではない。少なくともこれまで成功を収めてきた米国企業のやり方はそうである。 日本人や日本メーカーが得意としてきたインプリメンテーション指向の創造性の発揮に加えて、コンセプト指向の創造性を日本メーカーが組織としていかに発揮していくかが大きな課題である。そのためには、日本企業を日本人中心の企業と定義せず、もう少し広い視野で可能性を追求していくべきである。そして、コンセプトを研究所内の自己満足的なコンセプトで終わらせることなく、知的所有権型事業に結びつけて最終的には企業の収益に貢献できるように育てていくコツを会得することが重要である。
コンセプト創造ネットワーク組織の創設を ベンチャー・キャピタルの場合、資金の約半分は投資先の倒産によってまったく回収できないが、ほんの数パーセントの投資先が株式上場を果たせば採算が合うように経営される。ベンチャー・キャピタル経営のブロフェッショナルが資金を運用すれば、資本家の論理という面からだけでも正当なリターンが得られる。加えて、ベンチャー企業のネットワークの中に入ることで、米国でのインサイダー化の助けにもなるし、質の高い情報へのアクセスも可能となる。成功した企業からの投資のリターンとして、単なるキャピタル・ゲインだけでなく知的所有権の一部を期待することもできる。投資先に研究者を派遣することができれば、共同研究という意味での提携相手と考えることも可能となる。 この考え方に基づいて、少なくとも100億円以上の資金をコンセプト創造ネットワーク組織の原資として振り向けることが必要だ。中途半端な資金では、ベンチャー・キャピタル的な運用ができない。投資先の数が限られて確率論的アプローチが有効に働かないからである。100億円という資金は大手日本メーカーが本気になれば捻出できない額ではない。大手各社の数千億円という研究開発費や設備投資の考え方を若干でも、工業社会型から知能社会型に転換すればよいのである。 工業社会から知能社会へという変化が不可避のコンピュータ関連産業は、膨大な数の米国ベンチャー企業の総体としてのエネルギーによって牽引されている。この世界でコンセプト創造に主体的に関わり、生き抜いていくためには、少々突飛に見えても「彼らの流儀」に合わせた新しい事業の仕組みを作り上げていく挑戦が必要なのである。
「本当に日本メーカーにできるのだろうか」と問う前に こうした新しい方向性を実現していく上で、日本メーカーが克服しなければならない重要課題が3つある。第1に、知能社会化が進むにつれ「個人の能力」を組織の中でより重視しなければならなくなる。この環境変化に、年功序列・終身雇用を柱とする日本メーカーの雇用慣行が追いついていかないという問題である。第2に、米国でのインサイダー化のためのグローバル・スキルが、日本メーカーには欠如しているという問題である。そして第3に、これまでのコンセンサス・べースの意思決定プロセスではこの難局は乗り切れないという問題である。この3つの問題は複雑に絡み合いながら、これまで述べてきた戦略・構想の実現を阻む方向に作用するだろう。しかし、組織全体を徐序に変えていくための段階的アプローチと、新しいことに取り組むための特別組織(分社化も含めて)を設立する斬新なアプローチの両方をうまく組み合わせることで、この3つの問題を積極的に解決していかなければならない。創造的ビジョンとそれに基づくトップのリーダーシップによってしか、この難題の解決はできないと思う。 「本当に日本メーカーにできるのだろうか」と問いかけ、「簡単なことではない」と諦めるのはたやすい。ただその前に本稿で議論してきた可能性を「挑戦する心」を持って再考してほしい。確かに「本当に日本メーカーにできるのだろうか」という問いかけに対する客観的な一般解はない。ただ、真剣にこの方向を模索して成功する日本メーカーが、今世紀中に数社は出てくるのではないかと思う。一方、こうした戦略・構想を「簡単にはできそうもないから」という理由で近視眼的に諦めるメーカーは、他の成熟産業と同じように、人員削減も含めた縮小均衡で生きていかざるを得なくなってしまうだろう。 冒頭でも述べたが、産業構造の大変革の後は、新しいタイプの新しい企業がその担い手になればよいという考え方がある。もちろん、日本から新時代の担い手となる新しい企業が勃興してほしい。しかし同時に、これまでの日本のコンピュータ関連産業を支えてきた大手メーカーが衰退してよいとは思わない。これまでの40年間にわたる努力を無にしないためにも、新しい産業構造に適応していく真撃な努力が求められているのである。 ■
|
|
|
|
||
| ページ先頭へ | ||
| Home > The Archives > 中央公論 | ||
|
|
|
© 2002 Umeda Mochio. All rights reserved. |